目次
1 殺人事件とは
人を殺害した場合に成立する罪です。刑法第199条に規定され、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処されます。
重い犯罪であるということは、皆様もイメージできるかと思います。人の生命という最も保護すべきものを奪う行為について成立する犯罪ですから、刑罰についても重い内容が定められており、最も重い刑罰である死刑が科される可能性もあります。
殺人罪も十分に重い犯罪ではありますが、何らかの犯罪行為の結果として被害者を死亡させてしまった場合には、単なる殺人罪よりも重い犯罪が成立する場合があります。それが強盗致死や強制性交等致死等の罪になります。
殺人罪の法定刑として死刑も定められていますが、5年以上の有期懲役刑を選択することも可能です。刑法は、情状に酌量の余地が認められる場合などにおいて、その法定刑の下限を半分にすることを認めていますので、殺人罪に対して適用され得るもっとも軽い刑罰は懲役2年6月ということになります。そして、懲役3年以下の刑罰に対しては、執行猶予を付すことも可能ですので、殺人罪を理由に起訴された場合であっても、執行猶予が付される可能性もあるのです。
一方で、強盗・強制性交等致死の罪については、死刑又は無期懲役しか法定刑に定められていませんから、執行猶予が付される可能性はありません。また、強盗致死の罪については6年以上の懲役刑が科されることとなっておりますので、執行猶予付きの判決が宣告される可能性がない訳ではありませんが、基本的には執行猶予が付されないことを想定した法定刑を刑法は定めているものといえ、極めて重い刑罰が定められているものといえます。
ですから、人の命を奪ってしまうという結果が重大であることは共通していたとしても、何故、その人の命を奪うに至ったのかという点も、極めて重要だといえるのです。
このことは、罪を軽くする方向の事実としても認められます。例えば、意図的に人を殺害した場合と異なり、過失によって人の命を奪ってしまった場合には、50万円以下の罰金が科される旨が定められており、懲役刑すら定められていません。
なお、同じ過失であっても、自動車の運転等によって生じた交通事故によって人の命を奪ってしまった場合には、刑法ではなく自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が適用されることとなります。この法律は、極めて悪質な運転によって人の命を奪ってしまった場合において、刑法の罪名を適用するのでは、その刑事責任に見合った刑罰を科すことができないことから新たに制定された法律で、難しい法解釈が求められる論点もありますので、今回の解説からは省きます。
2 殺人罪の成立要件
刑法第199条は、「人を殺した者」に対して殺人罪を適用できる旨しか定めていませんから、「人」を「殺した」といえれば、殺人罪は成立することになります。
「人」について、「胎児」がいつ独立した「人」として扱われるのかという点や、死によって「人」でなくなる瞬間はいつなのかという点など、問題点がない訳ではありませんが、「人」かどうかが問題となるような事例は極めて限られています。
同様に、「殺した」という要件についても、意図的に他人の命を奪う行為であれば足り、その奪う方法について制限はありません。
したがって、刑法の条文だけを読むと、殺人罪の成立要件については、何も難しいことがないようにも思えてしまいますが、決してそういう訳ではありません。
殺人罪において問題となり得る争点として、「殺意」の問題があります。つまり、人の命が失われてしまったことは明らかであっても、意図的に命を奪おうとした行為によるものであったのかどうかが問題となるのです。
「殺意」と説明すると、日本語としては難しい言葉ではないように思えてしまいますが、「殺意」の有無の判断は実務上も非常に難しい問題の一つです。裁判員裁判が導入される際に、裁判員に対して難解な法律概念をどのように説明すべきかについて議論され、その内容について司法研修所がまとめているのですが、正当防衛、共謀、責任能力に並んで、殺意についても詳細に解説されており、事案毎に適切に専門家が説明できるように求められているのです。
「殺意」の問題について全てをここで説明することはできませんが、「殺そう」と思っていたか、「殺したくはない」と思っていたかというだけの問題ではないという点だけ説明させていただきます。
例えば、強く殺したいと思って水鉄砲を発砲しても、命が奪われる危険性はありませんから殺人罪は成立しませんし、殺したくないと願いながら心臓を狙って銃弾を発砲した場合には殺人罪が成立します。では、心臓ではなく掌を狙って発砲した場合はどうでしょうか?肘付近であった場合はどうでしょうか?掌を狙ったものの心臓に着弾してしまった場合はどうでしょうか?狙い通りに腕に着弾したものの多量の出血から亡くなってしまった場合はどうでしょうか?
実際の事案ではこのように単純に一言で表せませんので「殺意」の認定は非常に難しい問題となるのです。
「殺意」以外に問題となり得るものとして「因果関係」の問題があります。語弊を恐れずに簡単に説明すると、被告人の行為と被害者の死との間に、刑罰を科すほどの関係性があるかどうかを判断する概念になります。
「因果関係」が問題となった最近の事案として、高速道路であおり運転を行い、被害者の運転する車両を強制的に停車させ、その結果としてトラックが被害者の運転する車両に追突してしまい、被害者の命が奪われてしまったという事件があります。大きく報道された事件ですので、御存知の方も多いかもしれません。
被告人は、被害者の運転する車両に接触しておらず、被害者の方が命を落とす程の怪我を負ってしまったのは、その後に走行してきたトラックが追突したからです。
しかし、この裁判では被告人の行為と被害者の死との間に「因果関係」はあるものと判断されました。被告人の行為がなければ、トラックに追突されることもなかったはずですし、裁判所の判断に納得できる方も多いのではないでしょうか。
では、この事件が起きた現場がもっと交通量の少ない高速道路であった場合、「因果関係」は認められるでしょうか。一般道であった場合はどうでしょうか。車線が1つしかない道路であった場合はどうでしょうか。
交通量が少なくなればなるほど、そして法定速度が速くなければないほど、トラックが追突する危険性は小さくなり、「因果関係」は否定される可能性が高くなりますが、どこで線引きができるのかについては、具体的な事案に即して判断するしかないのです。
殺人罪で問題となり得る論点は、決して殺意と因果関係だけではありません。しかし、その2つだけみてみても問題点は多く、極めて単純な条文であるとはいえ、複雑な問題を孕んでいるのです。
3 関連する犯罪
(1)殺人罪(刑法第199条)
人を殺してしまった場合に成立します。刑法第199条に規定され、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処されます。
人の命が奪われてしまった場合に成立する最もシンプルな犯罪になります。
(2)強制わいせつ等致死傷罪(刑法第181条)
強制わいせつや強制性交等の犯行に及び、その結果として被害者の方の命まで奪ってしまった場合に成立します。刑法第181条に規定されており、強制わいせつ等の犯行に及んでいた場合には無期又は3年以上の懲役に処され、強制性交等の犯行に及んでいた場合には無期又は6年以上の懲役に処されます。
わいせつ行為や性交等の行為自体は、人の命を奪うことを目的になされる行為ではありませんし、人の命が直ちに失われる訳ではありません。
しかし、強制わいせつ等の行為に及ぶ際には、被害者に対して「暴行又は脅迫」等の行為に及ぶことがあり、その際に被害者を傷つけてしまうことはあり得ますし、その結果として被害者が亡くなってしまうこともあり得ます。
人の命を奪う行為の中でも極めて悪質であると考えられているため、法定刑は極めて重いものが定められています。
殺人罪と比較して法定刑が軽いように思えますが、それは強制わいせつ致死傷罪等については、「殺意」が不要とされていることが一つの理由となっています。つまり、被害者と無理矢理性行為ができればよく、殺すつもりがなかった場合であっても、強制わいせつ致死罪は成立するのです。
逆に、最初から殺害するつもりで犯行に及んでいる場合には、強制わいせつ等致死罪とは別に殺人罪も成立することになりますから、死刑を科すこともできるのです。
(3)傷害致死罪(刑法第205条)
他人の身体を傷つける行為を行い、その結果として人の命を奪ってしまった場合に成立する罪です。刑法第205条に規定されており、3年以上の有期懲役に処されます。
人を殺す場合、ほとんどのケースでその人の身体を傷つけることになりますから、条文だけ呼んだのでは、殺人罪との違いがハッキリしません。
傷害致死罪と殺人罪の違いは、「殺意」の有無になります。
「殺意」をもって人を傷つけた場合には殺人罪が成立しますが、「殺意」がなかった場合には傷害致死罪の成立にとどまります。その分、殺人罪よりも法定刑が軽く定められているのです。
(4)過失致死罪(刑法第210条)
過失により人を死亡させた場合に成立する罪で、刑法第210条に規定され、50万円以下の罰金に処されます。
これまで紹介した罪と比較すると、その法定刑が著しく軽く定められていることが分かります。殺害するつもりまでなくても、人を傷つけてしまうことは分かった上で、人に暴行を加えた場合等については、傷害致死罪が成立しますので、過失致死罪の成立が認められるのは、人を傷つけること自体についても故意が認められないような場合です。
また、人を傷つけるつもりがない行為であっても、上述したとおり、自動車の運転等に伴う行為の結果として、人を死亡させてしまった場合には、特別法によってより重い法定刑が定められていますので、過失致死罪が適用されるケースは極めて限られているものといえます。
例えば、非常に古い裁判例になりますが、お母さんが授乳中に眠ってしまい、その間に乳児を窒息死させてしまったようなケースで過失致死罪が適用されたことがあります。法定刑が極めて軽く定められていることも、このようなケースを前提とすると納得し易いのではないでしょうか。
同じように乳児がなくなってしまう事件として、自動車で買い物に行き、買い物中に乳児を車内に放置した結果、乳児が亡くなってしまうという悲惨な事件について、皆様も耳にする機会はあったのではないかと思います。
このような類型については、保護責任者遺棄致死罪等が適用されることが想定されますので、決して罰金50万円という軽い刑罰が科される訳ではありません。保護責任者遺棄致死については、別の論点が多く存在しますので、今回のページでは解説を省かせていただきます。
(5)業務上過失致死傷等罪(刑法第211条)
業務上の必要な注意を怠った結果として、人を死傷させてしまった場合に成立する犯罪で、刑法第211条に規定されており、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
過失致死罪とほとんど同じなのですが、単なる不注意ではなく、業務上求められる注意を怠った結果として人が亡くなってしまった場合に成立することになります。
過去の裁判例では、大規模な火災が生じた際に、防火シャッターを適切に閉鎖しなかったことなどを理由に、業務上過失致死傷罪が適用されたものなど、火災に関する事例が多く散見されます。
近年話題になったものとしては、ジェットコースターの脱輪等で利用客が亡くなってしまった場合に、この罪が適用されたとするニュースが大きく報道されていました。
人の命が失われることがないように、特に求められる業務に従事していたことを理由に、通常の過失致死の罪より重い法定刑が定められています。
ちなみに、刑法第211条には業務上過失致死傷罪だけでなく重過失致死傷罪も規定しています。業務上必要とされていた訳ではなくても、過失の程度が極めて重い場合には、重過失致死傷罪が成立することになります。
過失の程度が重いといっても、イメージがし難いと思いますが、例えば、闘犬用の犬を放し飼いにした結果として、子供を犬にかみ殺させてしまった事案等があります。
(6)逮捕等致死傷罪(刑法第221条)
不法に人を逮捕し、又は監禁した結果として、人を死傷させてしまった場合に成立する犯罪で、刑法第221条に規定されており、傷害の罪と比較して重い刑により処断する旨が定められています。
「傷害罪の刑と比較して重い刑」という法定刑の定め方がされているのは、傷害罪よりも上限も下限も重い刑罰を科すことを意味しています。したがって、もし被害者が亡くなってしまっている場合には、傷害致死罪と同様の法定刑が適用され、3年以上の有期懲役刑に処されることになります。
あくまでも逮捕又は監禁するための行為によって被害者が傷害を負った場合などに適用される罪になりますから、逮捕又は監禁中に、別の動機から被害者を殺害したようなケースにおいては、逮捕監禁の罪と殺人罪が成立することになります。
(7)強盗致死傷罪(刑法第240条)
強盗が人を死傷させた場合に成立する犯罪です。刑法第240条に規定されており、被害者が亡くなってしまった場合には、死刑又は無期懲役に処されることになります。
法定刑として死刑か無期懲役刑しか定められていないため、極めて重い犯罪とされています。
他の致死傷罪の条文と比較すると「よって」という文言が定められていないことなどから、殺意が認められる場合においても、強盗罪と殺人罪を成立させるのではなく、強盗致死罪が成立するものと考えられています。
この場合であっても、死刑という最も重い刑罰が法定刑として定められているために、不当に軽い刑罰が科されるということはありません。
強盗致死罪という文言からは極めて悪質な犯罪類型をイメージする方が多いように思います。しかし、詳細は強盗罪に関する解説に譲りますが、強盗の態様には様々なものがあり、万引きがバレてしまい、その場から逃走を試みる際に、店員等に傷害を負わせてしまうようなケースも
強盗致傷罪が成立することになりますし、被害者の方が不幸にもなくなってしまった場合には、そのようなケースにおいても強盗致死罪は成立し得るのです。
悪質な犯罪組織でなければ犯し得ない犯罪ということはできません。
(8)同意殺人罪(刑法第202条)
人の嘱託を受け若しくはその承諾を得た上でその人を殺害した場合に成立する犯罪で、刑法第202条に規定されています。6月以上7年以下の懲役刑に処されることとなります。
難しい日本語が用いられていますが、人から自分を殺してほしいと頼まれて殺害した場合や、自分を殺していいという承諾を受けた上でその人を殺害した場合に成立する犯罪です。被害者の方の同意があることから、他の犯罪と比較すると軽微な法定刑が定められているのです。
傷害罪の場合については、同意傷害罪の規定はありませんから、被害者の同意がある場合には犯罪は成立しないことになります。しかし、命については、いかに被害者の同意があったとしても、軽々しく奪うことは許されないものとして、同意殺人は自殺幇助と同じ条文で犯罪として定められているのです。
裁判例の中では心中未遂のような事案が散見されます。つまり、被害者と一緒に死のうとしていたにもかかわらず、一人だけ命が助かってしまったような事案です。既に被害者が亡くなってしまっており、被害者の方の話を聞くことはできませんから、本当に死ぬことについて同意をしていたのかという点の判断は極めて難しいものとなるのです。
4 よく御相談いただく行為(具体的態様)
(1)家族内での殺害
殺人罪は動機犯と呼ばれることもあります。つまり、万引きや横領などと異なり、何らかの強い動機がなければ、人の命を奪うという決断をすることは考え難いのではないかということです。
皆様も、他人に対して大きな憤りを感じたことは人生で何度か経験されたことはあると思いますし、「殺してやる」というようなセリフを自分で吐いたことはなくても、物語の中で耳にした機会は多いのではないでしょうか。
一方で、そのような感情になったことを経験したことがあっても、実際に相手を殺害しようとしたことはない方がほとんどだと思います。
自分が他人を殺害する様子というのを想像してみていただければ、相当に強い動機がなければ、そのようなことをすることはあり得ないと感じる方がほとんどなのではないでしょうか。
そして、そのように強い動機を抱くにあたっては、殺害する相手と何らかの関係性がなければ、通常はそこまで強い気持ちを抱くことはありません。10年以上前の調査になってしまいますが、殺人事件の被害者と加害者の関係について、約9割が面識のある人間同士で行われており、約3割が親族関係にあったと報告されています。
私自身が弁護人として担当した殺人事件の中にも、老々介護の末に自身や相手の将来を悲観して相手の人生に幕を下ろそうとした事案や、配偶者との関係が悪化したことから、子供の将来を悲観して子供との無理心中を図ろうとした事案等、家庭内で生じた殺人罪の案件があります。
このような事件の場合、加害者の親族と被害者の親族は共通していますから、残された遺族の方々は極めて不安定な状況に追い込まれてしまいます。遺族の方々としても、起きてしまった殺人事件について、どのように向き合うべきなのか整理することが難しいのです。
一方で、家庭内で生じた殺人事件の場合、加害者が被害者に対して悪感情を抱いておらず、短絡的な判断だという批判はあり得るとしても、被害者のことも考えた上で、殺害に及んでいるケースが多く認められます。このような場合、被告人に情状酌量の余地が大きく認められることから、同意殺人ではなく殺人罪として起訴された場合であっても、執行猶予付きの判決が宣告されることも珍しくありません。
そうすると、残された遺族の方々としても、裁判を終えた後、被告人とどのような関係を築いていくのかを考える必要があります。
弁護人としては、刑事裁判が終わるまでの間に、被告人と遺族との橋渡しを行う必要があるものといえるでしょう。
(2)致死罪として起訴される場合
関連する犯罪として紹介させていただいたとおり、人の命が奪われてしまった場合に成立する犯罪として、強盗致死罪などのように、何らかの犯罪行為に及んだ結果として、被害者を殺害するつもりではなかったものの、被害者の方の命を奪ってしまった事案があります。
そして、強盗致死罪や強制わいせつ致死罪などとの関係においては、本来の犯罪行為自体が極めて悪質であり、被害者の命を奪ってしまった行為について同情の余地がほとんど認められないケースが多いものといえます。
このようなケースにおいては、本来の犯罪行為と被害者の命が失われてしまった結果との因果関係について、安易に認めるのではなくしっかりと精査することが必要となります。それは、因果関係が認められることを前提とした場合、いかに万全な情状弁護を行ったとしても、極めて重い法定刑が予定されていることから、非常に重い判決が宣告される可能性があるからです。
また、殺人罪と同様に強盗致死罪や強制わいせつ致死罪として起訴されてしまうと、裁判員裁判対象事件として扱われることになります。裁判官による裁判と比較して、裁判員裁判による場合の方が一般的に刑が重くなるとまでは言えませんが、少なくともその手続により長い時間がかけられることとなり、逮捕、勾留されている場合には、身柄拘束期間が長期化するおそれがあるのです。
その意味では、捜査段階においては原則として黙秘することが最も被疑者の利益となることは間違いないのですが、裁判員裁判対象事件となるような罪名での起訴を防ぐために、捜査段階において一定の弁解を捜査機関に対して行うことも、弁護方針の1つとして検討する必要があるでしょう。
5 殺人罪の弁護方針
(1)犯罪事実を認める場合
ア 弁護方針
上述したように、殺人罪との関係では、家族内で事件が起きてしまうことが多く認められますし、親族間の事件ではない場合であっても、被告人と被害者との間で何らかの人間関係が認められるケースがほとんどです。
このような場合においては、何らかの強い動機がなければ人を殺害するという行為に及ばないはずですが、どのような理由があったとしても、正当防衛が成立するような極端なケースでなければ、人の命を奪うという行為が正当化されることはありません。また、正当化されないだけでなく、被告人本人にとっては大きな動機となり得る事情であっても、当たり前ですが裁判官も裁判員も人を殺害した経験を持たない方ばかりですから、そのような動機で人を殺害することについて同情的に考えてくれる方ばかりではありません。むしろ、どのような理由であっても、「そのような理由であれば、人を殺害する程に追い込まれてしまっても仕方ない」と考えてもらえるケースは極めて例外的であると理解する必要があります。
したがって、被告人本人としては、殺害するほかないと考えてしまう程に追い詰められていたとしても、そのような被告人の状況を理解してもらうためには、被告人がどのような状況でどのように生活してきたのかについて、裁判において十分に説明できるような準備が必要となります。
公判廷における被告人質問(被告人が裁判官や裁判員の前で直接話すことができる機会)が最も重要であることには変わりありませんが、被告人の話を裏付けるような証拠や証人を早期の段階から確保しておくことは必要不可欠でしょう。
特に、家族を殺めてしまうほどに追い詰められてしまった方との関係でいうと、他に協力的な家族がいらっしゃらない場合がほとんどです(そのような存在がいないから追い詰められてしまうのです)。
そうした場合に、今後の被告人の生活を支えてもらえるような専門家や福祉関係者へ早期の段階で接触を図る必要があります。
また、家族間で殺人罪が発生してしまった場合、被告人に対して執行猶予付きの判決が宣告され、刑務所に服役することなく社会内に復帰することとなる場合であっても、それまでとは大きく生活環境が変わることになるはずです。どのような生活環境で再起させるのかという点についても、周囲の方との協力の上、裁判の際に具体的に主張できるようにしておく必要があります。
イ 被害者への被害弁償
被害者は亡くなってしまっていますから、被害弁償をすることとなる場合、基本的には遺族の方と示談交渉を行うことになります。
上述したように、家族間で殺人事件が起こった場合、被害者の遺族と加害者の親族は共通していることが多く認められます。そのようなケースにおいて、残された遺族が加害者に対してどのような心情を抱いているかは、事案毎に大きな違いがみられます。
被告人が親族であることについて特段の意味を感じておらず、強い被害感情を抱いている方もいらっしゃいます(配偶者を殺害してしまった場合において、その配偶者の御両親が存命な場合には、強い被害感情を抱いているケースが多くみられます)。逆に、被害者の遺族でありつつも、被告人に対して同情的に感じていただけるケースもあります(介護疲れに起因して親を殺害してしまったケースにおいて、被告人の兄弟等については、被告人に介護を任せてしまっていた等の理由から、被告人を強くサポートして下さる方もいらっしゃいます)。
そうすると、被害者の遺族に対して求められる対応は事案毎に大きく違うことになります。家族であることとは無関係に宥恕を求めるために示談交渉を行うこともあり得そうですし、被告人の減刑を求める嘆願書等の作成に加えて、今後の被告人の生活環境の整備などについても証言していただくようなケースもありかもしれません。
ウ 再犯防止策
殺人罪の場合、強い動機が必要となるということは繰り返しお話してきました。したがって、人生において何度も人を殺害したいという強い動機を感じることは稀です。反社会的勢力に関係するような特殊な事案を除けば、再犯防止が強く求められる犯罪類型ではないといってよさそうです。
一方で、再犯について強く懸念する必要性がないといっても、裁判後の生活環境の調整は確実に必要になります。特に、被告人が高齢の場合には、元々生活していた場所に戻るのではなく、施設での生活を検討する必要があるかもしれません。
また、相続などの関係で複雑な問題が生じる可能性もあります。生活環境を変えるにあたっては、これまで居住していた不動産の処分等が必要となる可能性はある一方で、被告人が被害者の相続人にあたる場合、被告人が相続の欠格事由にあたる可能性がありますので、相続手続を直ちに進めることができない状況もあり得るのです。
刑事手続についてだけでなく、様々な法分野に関するアドバイスが必要となることもあるため、幅広い知識が刑事事件の弁護士には求められることになります。
(2)犯罪事実を認めない場合
単純な殺人罪において犯罪事実を否定する場合、多くは殺意や因果関係が問題になるように思いますが、他に犯人性の問題や正当防衛の成否等についても問題となり得ます。
また、単なる殺人罪ではなく、被害者の方の嘱託や承諾の有無が争点となるケースもあり得ます。
どのような主張が成立し得るのかについて、刑事事件の弁護士との間でしっかりと協議を行う必要性があります。その結果によって、原則通りに捜査機関からの取調べに対して黙秘するのか、自身の弁解を捜査機関に対して伝えるべきなのかという、捜査段階における弁護方針の根幹が変わり得るからです。
特に、人の命が失われてしまっているという重大な結果が生じている以上、捜査機関としても可能な限り精密な捜査を行うことが予定されています。一方で、他の犯罪類型であれば、公訴事実を証明するための根幹となる証拠である被害者の供述が、被害者の方がなくなってしまっている事件類型では獲得することができません。
この点についても、捜査機関の取調べに対してどのように対応するかを判断するにあたって、非常に難しい判断が必要となるでしょう。
6 法定刑一覧(参考条文)
①刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
②刑法第181条(強制わいせつ等致死傷罪)
1 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
2 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
③刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
④刑法第210条(過失致死罪)
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
⑤刑法第211条(業務上過失致死傷等罪)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
⑥刑法第221条(逮捕等致死傷罪)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
⑦刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
⑧刑法第202条(同意殺人罪)
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
<殺人事件に関する法定刑一覧>
| 犯罪の種類 | 法定刑 |
|---|---|
殺人罪 | 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役 |
強制わいせつ等致死傷罪 | 無期又は3年以上の懲役 |
傷害致死罪 | 3年以上の有期懲役 |
過失致死罪 | 50万円以下の罰金 |
業務上過失致死傷等罪 | 5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
逮捕等致死傷罪 | 傷害の罪と比較して、重い刑により処断 |
強盗致死傷罪 | 負傷させたときは無期又は6年以上の懲役 |
同意殺人罪 | 6月以上7年以下の懲役又は禁錮 |



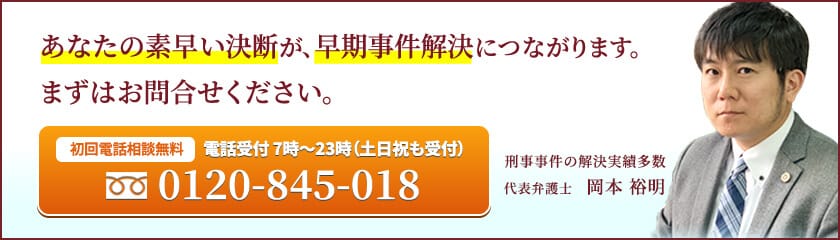

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー