目次
1 交通犯罪とは
ここでは、交通事故(自動車・自転車)や交通違反に関する交通犯罪を取り上げます。
交通犯罪には、
①「道路交通法」に違反する犯罪
②「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に違反する犯罪
この法律は、2014年5月に施行されたものです。
それまで、「刑法」にあった「自動車運転過失致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」を抜き出し、さらに新しい類型の犯罪を加えて刑を重くしたものです。
③「刑法」に違反する犯罪
自転車事故で被害者を怪我させてしまった場合などは、刑法違反として処罰される蚊のせいがあります。
これから、それぞれについて、解説します。
2 道路交通法に違反する犯罪
道路交通法に違反する犯罪には、速度超過(スピード違反)、酒気帯び・酒酔い運転、無免許運転などがあります。
ここで取り上げるのは、他人に怪我をさせていない違反類型です。
現実に事故を起こしてしまい、他人に怪我をさせた場合には、後記の「3 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に違反する犯罪」を参照してください。
道路交通法に違反する犯罪であっても、違反の程度が比較的軽いものについては、刑事罰に科されず、反則金を納めれば済むこととされてます。
例えば、一時停止違反、駐停車違反、携帯電話使用違反などの場合には、交通反則金を納めれば、裁判を免除されることがあります。
ただし、交通反則通告制度の適用がない一定程度以上の速度超過、酒気帯び・酒酔い運転、無免許運転などは刑事事件として処理されていきます。
酒気帯び・酒酔い運転、無免許運転などは、起訴されないだろうと甘く考える人もいますが、それまでの交通違反歴などによっては、すぐに起訴されてしまうこともあります。
また、逮捕・勾留される可能性もあります。ですから、できるだけ早い段階で弁護士を弁護人に選任した方が良いでしょう。
道路交通法第118条第1項第1号(速度超過)
1 次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転の禁止)
1 何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2第3号
次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両
を除く。次号において同じ。)を運転した者で,その運転をした場合において身
体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法第117条の2第1号
次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で,その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
道路交通法第64条第1項(無免許運転の禁止)
1 何人も,第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項,第百三条第一項若しくは第四項,第百三条の二第一項,第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。),自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2第1号
次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
3 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)に違反する犯罪
自動車を運転して他人に怪我をさせてしまったり、死亡させてしまった場合に適用されるのが、この法律です。
自動車運転死傷行為処罰法は、それまで、「刑法」にあった「自動車運転過失致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」を抜き出し、新しい類型の犯罪を加えて刑を重くしたものです。
自動車運転死傷行為処罰法に違反する犯罪については,道路交通法違反の場合のような、交通反則金の制度はありません。
そのため、一般的な刑事事件と同様に、警察において捜査がなされ、検察に送られてから処分が決まることになります。
この法律では、危険運転致死傷罪などが規定されていますが、危険運転致死傷罪については、人を負傷させた者は15年以下の懲役,人を死亡させた者は一年以上の有期懲役(20年以下の懲役)に処するとされています。
この法律に規定されている犯罪については、被害者が存在するため、被害者に対する被害弁償・示談交渉が重要です。
また、この法律違反の場合、自動車を運転する上での重要なルールを守れていないことになりますので、その点についての意識改善や再犯を起こさないための取り組みが重要になります。
この種の犯罪については、逮捕・勾留される可能性もあり、公判請求(起訴)される可能性も高くなります。
そのため、早い段階で弁護士を弁護人に付けて対応することが望まれます。
危険運転致死傷
最も重い刑罰が科される類型です。
この類型の犯罪は、交通事故を起こした理由が前方不注視や脇見運転などの過失ではなく、下の条文に示された通り、6つの特に危険な運転行為を故意に行ったときに適用される罪だからです。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
過失運転致死傷
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
4 刑法に違反する犯罪(自転車事故の場合)
自動車による人身事故については、自動車運転死傷行為処罰法に規定されていますが、「自転車」を運転中に人身事故を起こしてしまった場合については、刑法に規定されている犯罪である、過失致死傷罪(刑法第209条)や重過失致死傷罪(刑法第211条後段)が適用されます。
また、業務として(反復継続して)自転車を運転する者が起こした事故であれば、業務上過失致死傷罪(刑法第211条前段)が適用される可能性もあります。
自転車が車道を走行せずに歩道を走行することで歩行者と接触してしまう場合や、信号・標識を無視した運転により歩行者と衝突する場合などが見受けられます。
また、スマホを操作しながらの運転したりイヤホンを耳に着用したまま運転したりして、注意力が散漫になることで歩行者や他の自転車と衝突してしまう場合などがあります。
自転車による人身事故でも人を死亡させるような重大な結果が起こりうることが周知されてきたことから、2015年6月に道路交通法の自転車に関する部分が改正され、自転車の取締りが強化されました。
また、2015年10月に兵庫県で自転車保険勧誘が義務化されて以降、全国の自治体で義務化の流れが広まってきています。
これらの動きに伴い、警察・検察は、自転車による人身事故についても厳しく考え始めています。
そのため、ほんの少しでも注意していれば事故を避けられていたかもしれないのに、その注意を怠ったなどの重過失の場合や、複数の交通ルールに違反しているなど運転態様が悪質な場合、被害者が死亡したり重い怪我を負ったりした場合には、逮捕・勾留される可能性がありますし、最終的にはそのまま正式起訴や略式起訴がなされ、罰金刑や禁錮刑が科せられる可能性もあります。
この類型の犯罪にも被害者が存在しますので、被害者との示談成立の有無は処分内容に直結してきます。
ですから、自転車で人身事故を起こしてしまった場合には、早い段階で弁護士を弁護人として付けた方が良いといえます。
5 交通犯罪の弁護方針
(1)罪を認める場合の弁護方針
ア 交通事故で逮捕された場合は、早期釈放に向けた弁護活動を行います。
ひき逃げのケースでは、裁判官や検察官に「釈放するとまた逃げるのではないか?」と思われてしまい、他のケースに比べて身柄拘束が長期化する傾向にあります。
それ以外の交通犯罪においては、重大な結果が発生していても適切な弁護活動によって早期釈放を実現できる場合が多いといえます。
検察官は、交通事故の加害者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等の悪質な事故でない限り、不起訴になる可能性が高まります。示談を締結する前に起訴されたとしても、その後に示談が成立すれば、執行猶予になる可能性が相当高まります。裁判官も刑罰の重さを判断するにあたり、示談の成否を非常に重視しています。
イ 損害賠償と示談
自動車事故の損害賠償額は、けがの程度、通院期間等によって、ある程度、機械的に算出されます(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」通称「赤い本」という書籍に基準が示されています)。
そのようにして算出した金額を基礎として被害者と交渉することになります。加害者が任意保険(対人・対物無制限)に加入している場合、法的に適正な賠償は、保険によってなされます。
被害者が通院や入院を継続中の間は損害賠償額が定まらずに示談成立に至らない状況が続くことも多いため、先行して宥恕を得るために保険会社から支払われる示談金とは別に、加害者が直接謝罪金を支払うこともあります。任意保険に加入している場合は、判決までに示談が成立しなかったとしても裁判で有利に考慮される傾向にあります。
自賠責保険にしか加入していない場合、人身損害に関しては一定の限度でカバーされますが(死亡による損害…最高3000万円、傷害による損害…最高120万円、後遺症による損害…最高4000万円)、自賠責保険による支払い基準は損害賠償の基準よりも低い場合が多く、適正な損害賠償額自賠責保険基準額との差額を加害者が自己負担することもありえます。
また、自賠責保険では、物損についてはカバーされませんので、この点については加害者が自己負担で損害金を支払う必要があるでしょう。
ウ 被害者への謝罪
被害者にお会いしたり、手紙をお送りして謝罪します。通り一遍のことを述べるのではなく、自分の言葉で心をこめて謝罪することが重要です。
公判請求されてしまった場合には、謝罪文の写しを証拠として提出します。また、裁判官の前で被害者への思いを直接語ってもらいます。
エ 環境調整
高齢者による事故など、運転能力の低下が事故の原因と考えられる場合や重大事故を起こしてしまった場合には、運転免許を返納した上で車を売却したり廃車にすることも検討すべきです。それと同時に、車を使わなくても生活できるよう環境を調整していく必要があります。例えば、本人に「腰痛のため歩行が困難になり車を運転して買い物に行かざるを得なかった」という事情がある場合は、親族と同居したり、親族が買い物の送り迎えをする等の対処法が考えられます。
公判請求されてしまった場合には、車を売却したときの売買契約書、廃車した場合には廃車証明書、免許証を返納した際に交付される「申請による運転免許の取消通知書」等を証拠として提出し、すでに車を運転する環境にないことの立証を検討します。また、ご家族・ご親族の協力を得て環境改善を図る場合は、ご家族に情状証人として裁判官の前で具体的な改善策を語ってもらいます。
オ その他
交通事故の場合、加害者側の過失が100%とはいえないケースも多く存在します。
被害者側にも指摘できる過失がある場合にはその点について具体的に指摘します。
また、示談が成立しなかった場合、反省の気持ちを示すために交通遺児育英会などの団体へ寄付をします。公判請求された場合は、寄付金の領収書を証拠として提出します。
(2)否認する場合の弁護方針
ア 自白を取られないようにする
交通事故においては、事故車両や現場の痕跡と並んで、当事者の供述が重要な証拠となります。そのため、刑事裁判においては、「被疑者の言っていることが信用できるか否か」が大きな争点となります。
一度供述調書に記載されて認めた内容を後の裁判で覆すのは相当ハードルが高いといえます。
警察や検察などの捜査機関は、自分たちが思い描いた起訴しやすい構図に沿うように、被疑者に供述させようと働きかけます。被疑者としても、「相手が亡くなってしまった」、「相手がけがを負ってしまった」という負い目から、たとえ逮捕・勾留されていなくても、自分が思っていることを取調官に言うのをためらってしまい、取調官の言いなりになってしまうことが往々にしてあります。
ご本人が逮捕・勾留されている場合はもちろん、逮捕・勾留されていない場合も、適切な取調べを受けられるよう弁護士が継続的にバックアップしていきます。
イ 不利益な供述の信用性を争う
交通事故では、「被害者や目撃者の供述が信用できるか否か」も大きな争点となります。人間の記憶は時の経過とともに衰えていくものですが、取調べが進むにしたがって、被害者や目撃者の供述がより詳しくなっていくことがあります。また、異なる時点で作成された複数の供述調書の間で、同一の場面についての供述内容が不自然に変化していることもあります。
これらは取調官による誘導や働きかけ、被害者・目撃者の捜査機関への迎合的態度を示唆するものです。弁護士が被害者や目撃者の供述調書を検討したり、反対尋問を行うことによって、これらの供述の不合理性を炙り出します。
ウ 鑑定を行う
交通事故事件では、運転者の過失の有無を判断するため、しばしば専門知識を駆使した科学的分析が必要となります。
その場合、捜査機関は専門家に鑑定を依頼して必要な調査を行わせます。鑑定の例としては、道路上のタイヤ痕や車体のダメージから衝突直前の車の速度を明らかにする速度鑑定が挙げられます。捜査機関が実施した鑑定には、信頼性について疑問がある場合も少なくありません。
その場合、別途費用がかかりますが、弁護士と協力し、加害者側でも専門家に依頼して鑑定の実施を検討します。
具体的に捜査機関側の鑑定結果の信頼性の疑義が指摘できる場合には、裁判所に鑑定を実施するよう請求することも視野に入れます。




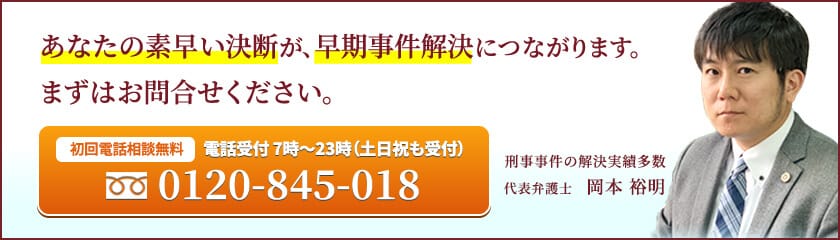

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー