無罪となったら必ず補償を受けられるのか
- 冤罪によって逮捕、勾留された場合には刑事補償を求めることができる。
- 例外的に虚偽自白があった場合などにおいては、刑事補償が認められないこともあり得る。
- 特に、被疑者段階における刑事補償を求めるためには、認められるためのハードルが極めて高く、専門家のアドバイスが必要不可欠である。
刑事補償法という法律を御存知でしょうか。
日本の刑事裁判は極めて有罪率が高いことで知られていますし、裁判が確定するまでの間の身体拘束期間が長いことについても、諸外国から強く批判されています。
したがって、冤罪によって逮捕、勾留され、長期間の裁判を戦い、結果的に無罪を勝ち取れた場合であっても、社会的信用は既に失われてしまっていますし、著しく大きな精神的苦痛を受けることになります。
冤罪を理由とする逮捕、勾留、起訴は許されるものではありませんが、他方で、人が行うことである以上、誤りが発生する可能性は否定できません。
そこで、そのような大きな損害を被った方の補償を行うために定められているのが刑事補償法になります。
しかしながら、そもそも無罪判決の宣告自体が珍しいので、刑事補償について問題となることは多くありませんし、一般の方にもあまり知られていないように思います。
今回は刑事補償について解説をしていきたいと思います。

目次
1.刑事補償を定める法律

(1)憲法上の要求
刑事補償の詳細を定めているのは刑事補償法なのですが、実は、一定の場合に刑事補償を行うべきであることは憲法上の要求でもあるのです。
憲法
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
このように憲法は、無罪の裁判を受けた場合には、法律の定める内容に則って補償を求める権利を認めています。つまり、憲法自体は刑事補償の内容を定めていませんが、国は刑事補償の詳細を定める法律を制定しなくてはなりません。
その結果として定められている刑事補償法は、憲法の要求を受けて制定されている法律ですから、無罪の裁判を受けたにもかかわらず、その一部に対してしか補償を行わないというような内容を定めることはできないはずです。
もっとも、憲法第40条も、単に無罪の裁判を受けた場合ではなく、「拘留又は拘禁された」という条件を定めていますので、在宅のまま捜査が行われ、在宅のまま裁判を受けて無罪となった場合には、憲法上も、補償を受ける権利は認められていないということになります。
(2)刑事補償法の定め
では、実際に刑事補償法はどのような場合に刑事補償を行う旨を定めているのかを確認してみましょう。
刑事補償法
(補償の要件)
第1条
1項 刑事訴訟法による…手続において無罪の裁判を受けた者が同法…によって未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
2項 上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によってすでに刑の執行を受け…た場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
(補償をしないことができる場合)
第3条
左の場合には、裁判所の健全な裁量により、補償の一部又は全部をしないことができる。
1号 本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為することにより、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至ったものと認められる場合
2号 一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、 他の部分について有罪の裁判を受けた場合
まず、第1条によって刑事補償を求めるための要件が定められています。ここで補償を請求することができるとされているのは、「抑留又は拘禁による補償」ですから、憲法の定めと同様に、在宅のまま手続が完結した場合には、補償を求めることはできません。この点については在宅での手続の場合であっても、被告人の方が被る精神的苦痛や、起訴されたことに伴う社会的信用の失墜等、大きな損害を被っている訳ですから、何らかの補償が必要だと個人的には強く感じるところですが、現行法上は逮捕、勾留されている場合に限定されているのです。
なお、第1条2項は、再審等の手続によって無罪判決が宣告されるケースについて定めています。この場合、逮捕、勾留期間だけでなく、刑務所に服役していた期間についても補償されなければ不当ですから、そのような期間についても補償を求めることができる旨が定められているのです。
2.例外的に補償がなされない場合

(1)補償が不要となる理由
先程、刑事補償は憲法上の要求であることから、刑事補償法によって、刑事補償を不要とするような規定は設けられないはずであると説明させていただきましたが、刑事補償法第3条は例外的に補償が不要となる場合を定めています。
刑事補償法第3条が憲法に違反していないことについては、憲法第12条が「この憲法が国民に保障する自由及び権利は…これを濫用してはならない」と規定しており、同条のいう権利が「濫用」されている場合や、そもそも憲法第40条によって刑事補償を求める権利として認められていない場合を具体化したに過ぎないと理解されています。
1号は、自ら虚偽の供述をすることによって、捜査機関の誤らせた結果として、逮捕、勾留等がされてしまった場合について、権利の濫用と捉えて、刑事補償を不要とする規定です。
そして、2号については、複数の罪の内の1部について無罪であったとしても、他に逮捕や勾留を正当化する罪について有罪であった場合には、その有罪であった罪にかかる逮捕、勾留であったとして刑事補償を不要とする規定と理解することができます。
(2)「虚偽の自白」の意味
刑事補償法第3条が補償を不要としている意味についてはイメージし易いと思います。しかし、「虚偽の自白」があった場合に補償は常に不要といえるのでしょうか。自業自得だと片付けてしまえるでしょうか。
再審によって無罪判決が宣告された事件においても虚偽の自白が証拠とされていたことが明らかとなっています。そのような著名な事件ではなくても、逮捕、勾留された上で、捜査官の取調べに耐えかねて、行ってもいない罪を犯したと自白してしまうケースは多く存在します。
そのようなケースにおいて、虚偽の自白をするまで追い詰められてしまっているにもかかわらず、虚偽の自白をしたことによって拘束期間が長引いたのは自業自得で刑事補償は不要であるといえるでしょうか。
この点について、刑事補償法第3条の文言からは読み取りにくいですが、そのような虚偽自白の場合についてまで、刑事補償が不要とは理解されていません。あくまでも、暴力団組織等において親分を守るために、子分が身代わりとなって虚偽の自白をしたようなケースに限定して、刑事補償は不要となるものと理解されています。
つまり、積極的に「捜査又は審判を誤まらせる目的」があった場合にのみ、例外的に刑事補償は不要となるのです。
3.裁判例

では、どのような場合に刑事補償が不要とされ、どのような場合に刑事補償を求めることができるのかについて、実際の裁判例を確認したいと思います。
刑事補償が不要とされた最近の裁判例として、東京高決令和2年7月15日があります。この事件の被告人は、交際相手を庇うために、本当は交際相手が自ら覚醒剤を使用していたにもかかわらず、自分が交際相手に覚醒剤を注射したと虚偽の供述を行っていました。
被告人は、取調べの際に、交際相手の供述と矛盾する弁解をすれば拘束が長引く旨を伝えられたために虚偽の供述をせざるを得なかった旨を主張したようですが、交際相手に迷惑を掛けたくなかったと主張していた点が重視され、刑事補償法第3条1号が適用され、刑事補償は認められませんでした。
共犯者供述と整合しない旨を取調べに際して伝えられることは珍しい事ではありませんから、被告人の供述を排斥することはできないように思いますが、被告人自身も交際相手を庇いたいという気持ちはあったようで、この点が重視されてしまったようでした。個人的には、刑事補償法第3条が適用される限界事例のように感じています。
一方で、東京高決平成26年7月11日は刑事補償を認めた裁判例です。この事案の被告人は、窃盗罪として逮捕、勾留されており、その事実を認めていたものの、起訴される直前になって、被害者との同意に基づき金銭を預かったのだと弁解を変更したようです。その理由については判決文からは明らかになっていませんが、当初の虚偽自白は、「捜査又は審判を誤まらせる目的」があったものとされています。
しかし、東京高裁は、捜査機関に対して真実を打ち明け、再捜査を求めた後の拘束期間について、刑事補償を行う旨を判断しています。
4.被疑者段階

以上のとおり、例外はあるものの、無罪判決が言い渡された場合には、刑事補償を求める権利が認められています。
では、逮捕、勾留された後、起訴されることなく不起訴を理由に釈放された場合には、刑事補償を求める余地はないのでしょうか。起訴されてしまった場合と比較すれば、冤罪を理由に拘束されてしまった期間は短くなるはずですが、逮捕、勾留によっても相当な期間は拘束されることになりますし、その期間が理由となり失職するなどの大きな損害を被るケースも珍しくありません。
憲法は無罪判決が言い渡された場合のみを規定していますが、不起訴となった場合の刑事補償については、被疑者補償規程が法務省の訓令として定められており、一部の場合には刑事補償を求めることが可能とされています。
被疑者補償規程
(補償の要件)
第2条
検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しな い処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をするものとする。
(立件手続を行う場合)
第4条
補償に関する事件の立件手続は、次の場合に行う。
(1) 被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、事件事務規程第72条第2項に定める「罪とならず」又は「嫌疑なし」の不起訴裁定主文により、公訴を提起しない処分があったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる事由があるとき。
(3) 補償の申出があったとき。
被疑者段階における刑事補償を受けることを困難にしているのは、「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由」が求められている点です。刑事手続においては、被告人が罪を犯したことを検察官が立証する必要があり、立証ができない場合には無罪判決が宣告されなければなりません。
しかし、被疑者補償規程においては刑事補償を求めるにあたって、「罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由」が逆に求められることになります。
実際に、被疑者補償規程第4条は補償に関する事件の立件について、「嫌疑なし」等を挙げており、「嫌疑不十分」を列挙していません。
したがって、被疑者段階において刑事補償を受けるには、犯罪に及んでいないことが明らかなようなケースに限られてしまうのです。
5.まとめ

刑事手続における被疑者、被告人や弁護人(刑事事件の弁護士)の目標は、無罪判決や不起訴処分です。しかし、その目標を達成した後も、刑事補償を得られるかどうかという大きな問題があります。
上述したとおり、不起訴処分の場合には、刑事補償を受けるためのハードルが大きく、刑事事件の弁護士の助力は不可欠なものといえますし、無罪判決が言い渡された場合であっても、例外的に刑事補償がなされないケースは十分想定されるのです。





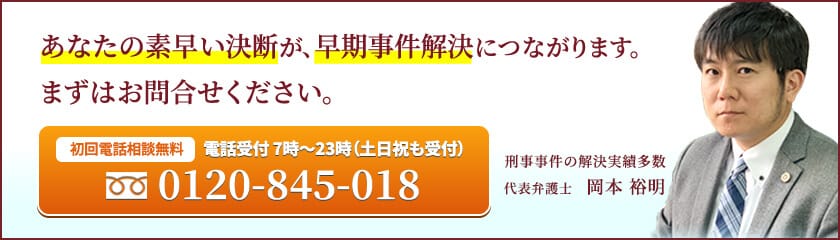

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー