未決勾留日数とは
- 未決勾留日数は刑期に算入され得る。
- 算入の有無や日数に関する具体的な基準は、一部を除いて法律で明確に定められていない。
- 裁判所の裁量に委ねられている部分が極めて大きく、経験及び知識のある弁護人からのアドバイスが求められる。
「未決勾留日数」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。
勾留日数だけであれば、勾留されている日数を意味する単語として理解できますが、「未決」という単語がついていますから、何かが決まっていない状況下における勾留日数を意味する単語になりそうです。
何が「未決」なのかというと、判決が未だに確定していないことを意味しています(とはいえ、もともと「勾留」も、刑罰の一種である「拘留」と異なり、判決が確定するまでの間に行われる身体拘束ですから、「既決」の「勾留日数」というのはほとんど考えられないのですが)。
勾留日数が長ければ長い程、刑罰としての制裁ではなく、裁判への出廷を確保するなどの目的で、長く身体拘束がなされていることを意味します。
そして、そのような身体拘束期間が長期に及んだ場合には、「勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は…決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない」(刑事訴訟法第91条1項)と定められており、勾留日数は保釈を許可するかどうかを検討する際の考慮要素ともなっているのです。
しかし、「未決勾留日数」という言葉が問題となるのは、保釈の許否ではなく、判決宣告の場面になるでしょう。
判決宣告の場面で何故「未決勾留日数」が問題となるのでしょうか。それは、実際に宣告された刑罰から、「未決勾留日数分」が差し引かれるという意味を持つからです。
今回は、「未決勾留日数」がどのような意味を持つのかについて解説させていただこうと思います。

目次
1.刑法上の定め

冒頭で、「未決勾留日数」については、実際の刑期から差し引かれる日数だと説明させていただきました。やや不正確な表現ですので、法律上どのように定められているのかについて確認してみましょう。
刑法
(未決勾留日数の本刑算入)
第21条
未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
刑法は、「未決勾留日数」について、第21条しか定めておりません。
まず、このような定めが置かれているのは、勾留は刑罰ではないものの、国家による身体拘束という点で懲役刑や拘禁刑のような自由刑と同じ側面が認められます。そのため、身体を拘束されていた期間について、刑罰の執行を受けていたものとして扱おうという趣旨によるものです(ですから懲役1年の判決に対して、未決勾留期間として60日が算入された場合、60日は既に服役したものとして扱うのであって、懲役10月の刑が宣告された訳ではないので、「刑期から差し引く」という表現は正確ではありませんが、今回はこの違いを無視して解説させていただきます)。
とはいえ、「未決勾留」を問題としている訳ですから、国家による身体拘束としての側面が認められる手続について、全て刑罰の執行を受けていたものとして扱われる訳ではありません。例えば、出入国管理及び難民認定法第52条5項には、「入国警備官は…退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場…に収容することができる。」と定めています。
この定めによって収容されていた期間については、刑罰の執行を受けたものとして扱うことはなく、刑期から差し引かれることはありません。
しかし、例えば少年法第53条は、「少年鑑別所に収容中の日数は、これを未決勾留の日数とみなす」と定めていますし、刑事訴訟法第167条6項も「第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。」と定めています。なので、鑑別所に収容されていた期間や、鑑定留置として病院に入院させられていた期間など、勾留ではない身体拘束の場合であっても、「未決勾留日数」として扱われる場合もあります。
2.未決勾留日数の計算方法
(1)必ず算入される期間

このように、「未決勾留日数」として取り扱われるかどうかは、他の法律に定められているかどうかを確認する必要があります。
一方で、刑事裁判に関する通常の勾留の場合も含めて、「未決勾留」がいつからいつまでを意味するのかについて、具体的に法律は定めていません。
この点については、刑法第21条のいう「未決勾留の日数」とは、勾留状が執行されてから、判決が宣告される前日までの日数をいうものと解されています。判決が宣告された後も、控訴や上告をすれば判決は確定せず、「未決勾留」の状態は続くはずなのになぜでしょうか。
それは、上訴に関連する「未決勾留の日数」については、刑法ではなく刑事訴訟法に定められているためです。
刑事訴訟法
第495条
1項 上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
2項 上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
1号 検察官が上訴を申し立てたとき。
2号 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
刑事訴訟法第495条1項によって、「上訴の提起期間中の未決勾留の日数」は、その全部を刑に通算する旨が定められています。刑法第21条のように「算入することができる。」という定めではありませんから、必ず差し引かれることになるのです。
「上訴申立後の未決勾留の日数」は除外されていますので、控訴審や上告審の判決が宣告されるまでの期間が全て通算される訳ではなく、必ず差し引かれるのは、控訴するかどうかのわずかな期間に限られます。
一方で、控訴した後の期間についても、検察官が控訴を申し立てた場合や、第一審判決が破棄された場合には、全期間が通算されることになります。
(2)計算式

では、上述したように、必ず算入するように法律が定めている場合以外のケースでは、刑期から差し引かれる期間はどのように決められているのでしょうか。
「全部を算入できる」と刑法第21条は定めていますが、実際に未決勾留の日数全日が算入されることはほとんどありません。
確かに、国家による身体拘束という意味では、刑罰としての懲役刑や拘禁刑と未決勾留に同じ側面は認められます。しかし、勾留も刑事裁判を機能させるにあたって必要だからこそ行われているものです(我が国の刑事司法は、「人質司法」と強く非難されており、私自身も安易に被告人が勾留され過ぎていると考えていますが、この点も今回の解説ではおいておきましょう)。
そこで現在は、捜査や裁判のために必要な期間に関する身体拘束については被告人が甘受すべきであるため、刑期から差し引かずに、その期間を超える部分について算入するという運用がなされています。
個人的には、身体拘束がなされている以上、全ての期間について算入されるべきだと考えていますが、少なくとも現在の日本の裁判所はそのようには考えていない訳です。
では、どのように算入期間は計算されているのでしょうか。
先ほど説明した、捜査や裁判のために必要な期間を特定し、それ以外の期間を算入することになる訳ですから、本来的には算入する日数を算出するための計算式は存在せず、事案毎に裁判官が判断すべきです。
しかし、それでは裁判官に大きな裁量を与えすぎてしまうことにもなりかねませんし、予測が極めて困難となってしまいます。
そこで、次のような計算式が用いられると解されています。
まず、起訴前の勾留については捜査に必要な期間として捉え、そもそもの計算式に組み込まず、起訴後の勾留日数を基準とします。そこから、初回の公判期日の準備のために必要不可欠な期間として30日を差し引きます。2回目以降の公判期日の準備の必要不可欠な期間として10日を差し引きます。残りの日数が算入すべき「未決勾留日数」になるということです。
しかし、裁判員裁判のように、初回の公判期日が行われるまでの間に何度も公判前整理手続が行われるようなケースについては、起訴から初回の公判期日までに1年以上の身体拘束が継続されることもあり、上記計算式では妥当な結論が導けない場合もあります。
あくまで上記計算式は参考程度のものであると御理解いただければと思います。実際に、裁判員裁判を念頭においた別の計算式なども提唱されており、一律に計算できるものではないのです。
3.満つるまで算入とは

「満つるまで算入」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。何に満つるまで算入するかというと、宣告された刑期に満つるまでという意味です。
具体的には、「被告人を懲役〇年に処する。未決勾留日数中、その刑期に満つるまでの分をその刑に算入する。」という形で判決は宣告されます。
このような判決が宣告された場合、宣告刑の全てについて刑を執行した扱いになりますので、実際に刑務所に服役する必要はなくなります。
同じような扱いは懲役刑などに限らず、罰金刑でも行われます。罰金刑の場合、「未決勾留日数」という身体拘束の問題を金銭に換算しなくてはいけませんので、判決では、「被告人を罰金○○万円に処する。未決勾留日数のうち、その1日を金○○円に換算してその罰金額に満つるまでの分を、その刑に算入する。」という形で宣告されます。現在は、ほとんどの裁判において1日あたりの金額は5000円とされています。
4.未決勾留日数と弁護活動

被告人が無罪を主張している場合、弁護人としては、未決勾留日数を算入すべき刑罰そのものを科すべきではない旨を主張することになる訳ですから、未決勾留日数について主張することは原則的にないものと思われます。
一方で、情状弁護によって減刑する場合、迅速に公判を終わらせる(可能であれば即日結審)ことや早期に保釈の許可を得ることを目的とすることになろうと思いますから、未決勾留日数が最大の論点となることは考え難いように思われます。
しかしながら、最高裁判所平成14年6月5日決定(判例時報1786号160頁)は、「第一審判決が未決勾留日数を本刑に全く算入しなかったのは…刑の量定に関する判断を誤ったものといわざるを得ないが、未決勾留日数の算入に関する判断は、本来判決裁判所の裁量にかかるものであることなどにかんがみると、上記第一審判決を是認した原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない。」と判示しています。
この事案における被告人は5万円の罰金刑を宣告されており、未決勾留期間は93日間でした。未決勾留期間が更に長期に及んでいた場合などにおいて、裁判所に認められた裁量を大幅に超えたとして、上記最高裁決定と異なる判断がなされる可能性がない訳ではありませんが、上訴審において算入される未決勾留日数を増加させる主張は退けられる可能性が高そうです。
そこで、主たる論点にはなり難いとしても、無罪を主張していない事案においては、減刑に加えて算入されるべき未決勾留期間についても適切に主張することが求められるものといえます。
5.まとめ

今回は、未決勾留日数について解説させていただきました。未決勾留日数として刑期に算入される日数について、その計算式が法律で具体的に定められている訳ではありませんし、罰金刑に算入する場合において、1日あたりの金額をいくらと定めるべきかについても具体的に定められていません(刑事訴訟法第495条3項は「4000円」と定めていますが、刑法第21条の算入との関係では同項を参考にして4000円とするのではなく、5000円とされるケースが多いことは本文で解説させていただきました)。
つまり、裁判所に大きな裁量が認められているといえます。法文を確認しても内容を把握できない以上、経験のある弁護士のアドバイスは必要不可欠なものといえるでしょう。


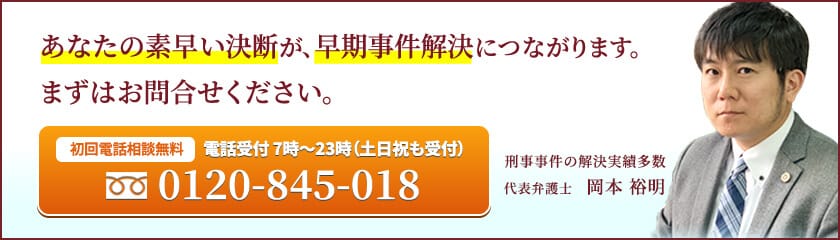

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー