1.保護観察処分とは何か
全件送致主義のもと原則的に家庭裁判所に必ず送致されるということが、必ず家庭裁判所の処分を受けることになるという意味ではないことについては解説させていただきました。付添人弁護士としては、審判不開始決定をまずは目標とし、次に家庭裁判所の審判において不処分決定を得ることを目標とすることになります。
一方で、成年事件であれば不起訴となることが目に見えている事案であっても、被疑者が少年の場合、少年に対して何らかの保護処分が下される可能性は低くありません。
それは、少年の更生に向けて必要な処分ですから、家庭裁判所は少年を処分することについて謙抑的な態度をとらないためです。
したがって、家庭裁判所から何らかの保護処分が下されることが不可避である場合や、少年の更生に向けて、公的な機関のサポートが必要であると思料する場合、付添人としては、少年の身体を施設に収容することのない保護処分を目的に弁護活動を行うことになります。それが、保護観察処分です。
保護観察処分は、法律上次のように定められています。
少年法
第24条家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
1号 保護観察所の保護観察に付すること。
少年法は、審判の結果として、少年を保護観察に付することができる旨は定めていますが、その内容について特に定めを置いておりません。
では、どの法律に定めがあるのでしょうか。
更生保護法
第48条次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。
1号 少年法第24条1項1号の保護処分に付されている者
第49条1項 保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、第57条及び第65条の3第1項に規定する指導監督並びに第58条に規定する補導援護を行うことにより実施するものとする。
第50条
2項 保護観察処分少年又は少年院仮退院者に対する保護観察は、保護処分の趣旨を踏まえ、その者の健全な育成を期して実施しなければならない。保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。
第51条
1号 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。
2号 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること。
イ 保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは、これに応じ、面接を受けること。
ロ 保護観察官又は保護司から、労働又は通学の状況、収入又は支出の状況、家庭環境、交友関係その他の生活の実態を示す事実であって指導監督を行うため把握すべきものを明らかにするよう求められたときは、これに応じ、その事実を申告し、又はこれに関する資料を提示すること。1項 保護観察対象者は、一般遵守事項のほか、遵守すべき特別の事項(以下「特別遵守事項」という。)が定められたときは、これを遵守しなければならない。
第57条
2項 特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第52条の定めるところにより、これに違反した場合に…少年法第26条の4第1項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。
1号 犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に 結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと。
2号 労働に従事すること、通学することその他の再び犯罪をすることがなく又は非行のない健全な生活態度を保持するために必要と認められる特定の行動を実行し、又は継続すること。
4号 医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として法務大臣が定めるものを受けること。
6号 善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。
7号 その他指導監督を行うため特に必要な事項保護観察における指導監督は、次に掲げる方法によって行うものとする。
1号 面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。
2号 保護観察対象者が一般遵守事項及び特別遵守事項(以下「遵守事項」という。)を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活し、及び行動するよう、必要な指示その他の措置をとること。
3号 特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること。
以上のとおり、保護観察処分の内容は更生保護法に定められています。保護観察処分は、成年の刑事裁判において懲役刑の執行猶予判決と共に付されることがあり、少年事件と成年の刑事事件と共通する制度でもあるのです。
そして、保護観察処分の主たる内容は、保護司による指導監督であり、保護司は少年や少年の保護者との面談等を通じて、少年を指導することになります。
また、少年及び少年の保護者に対しては、保護観察中に遵守すべき事項が定められることになります。一般遵守事項については、全ての保護観察との関係で遵守が求められるもので、特別遵守事項については、個別の事案との関係で必要なものについて、保護観察官が定めるものです。また、保護観察官は家庭裁判所の意見を聞いて、特別遵守事項を定めることになりますから、審判の際に裁判官から特別遵守事項について、直接少年及び少年の保護者に対して伝えられることも多いです。
2.保護観察処分中の生活について
以上のとおり、保護観察処分とは、保護司との面会等を通じて、少年の更生を図る処分になります。身体の収容を伴わない処分ですから、審判において保護観察処分を言い渡された場合には、その日の内に自宅に帰ることができますし、通学等も可能ですから、少年の生活環境を変えることなく少年の更生を図ることができます。
ですから、事案によっては保護司や保護観察官等の協力がなくても少年の保護者のみによって少年の指導・監督を行えると感じる事案もありますが、保護観察処分に付されること自体には、少年に対する悪影響は大きくないものと言えます。
しかし、保護観察処分には他の意味もあります。それは、保護観察中の再犯については、極めて厳重な処分が予想されるということです。
成年の事件については、保護観察中の再犯については、執行猶予を付することができない旨が法律に定められています(刑法第25条2項)。少年事件においては、保護観察中に再度犯罪行為に及んだ場合、再度保護観察処分に付することが禁止されてはいませんが、保護観察処分によって十分に更生を図ることができなかった事を理由に、少年院送致等、より厳重な処分に付されるのが通常です。
また、保護観察中は上述したように、一般遵守事項及び特別遵守事項が定められていますから、大きな負担とはならない事項が多いとはいえ、そのような遵守事項に違反することがないように生活する必要があります。
この遵守事項に違反した場合については、次のように定められています。
更生保護法
第67条1項 保護観察所の長は、保護観察処分少年が、遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。
2項 保護観察所の長は、前項の警告を受けた保護観察処分少年が、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、少年法第26条の4第1項の決定の申請をすることができる。少年法
第26条の4更生保護法第67条第2項の申請があつた場合において、家庭裁判所は、審判の結果、第24条第1項第1号の保護処分を受けた者がその遵守すべき事項を遵守せず、同法第67条第1項の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守すべき事項を遵守しなかつたと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、その保護処分によっては本人の改善及び更生を図ることができないと認めるときは、決定をもつて、第24条第1項第2号又は第3号の保護処分をしなければならない。
つまり、遵守事項違反に対して保護観察官は少年に対して警告を発することができることに加え、その遵守事項違反の程度が重い場合には、家庭裁判所に少年院等に送致するように申請されてしまうことになるのです。
保護観察期間中は、遵守事項に違反することがないように、適切に少年を指導する必要性が高く認められるのです。
3.保護観察の期間について
少年事件における少年審判の際に、裁判官は保護処分決定の期間を言い渡すことはありません。成年の刑事事件においては、懲役刑の期間等については明確に宣告することと比較すると大きな違いが認められます。
それは、保護観察等の保護処分の継続期間については、少年の更生の程度に応じて、保護観察官等によって判断されるからです。
保護観察の期間についての定めは次のとおりです。
更生保護法
第66条保護観察処分少年に対する保護観察の期間は、当該保護観察処分少年が20歳に達するまで(その期間が2年に満たない場合には、2年)とする。
第69条保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。
つまり、原則として保護観察の期間は2年とされており、保護観察を継続する中で、十分に少年が更生したと考えられる時には、2年を経過する前であっても、保護観察を解除することができるのです。
一方で、保護観察処分には一般短期保護観察等と呼ばれ、2年よりも短い期間で終了することを予定するものもあります。この運用は、「段階別処遇による体系的な保護観察の実施について」という通達によって定められており、一般短期保護観察処分に付する旨を家庭裁判所から定められた場合、多くのケースにおいては半年を目途に保護観察が終了することになります。
4.小括
保護観察処分について簡単に解説させていただきました。保護観察処分は、身体収容を伴わない処分ですし、保護司や保護観察官による指導に、少年の更生を期待することができます。また、保護観察中の生活態度が良好であれば、保護観察期間は長期に及ぶことは稀です。保護司も親身に少年や少年の保護者と接してくれる方が多い印象です。敵視することなく、家族ぐるみで付き合うべきだと感じています。
一方で、保護観察中の遵守事項に違反した場合には、最悪の場合少年院等に送致されてしまう可能性もあります。遵守事項についてはしっかり意識した上で生活させる必要があるでしょう。
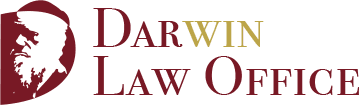
 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー