1.出廷は不要
民事事件と異なり、刑事事件においては、被告人の出廷が必要不可欠です。しかしながら、控訴審においては被告人の出廷は、開廷のために必要な要件とはされていません。
刑事訴訟法
第283条
被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。
第284条
50万円…以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。
第285条
1項 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
2項 長期3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円…を超える罰金に当たる事件の被告人は、第291条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
第286条
前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
第390条
控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円…以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
以上のとおり、第一審においては、極めて例外的な場合を除いて、被告人が出頭していなければ開廷できないとしているのに対して、控訴審では原則的に被告人の出頭を求めていないのです。
このような法律の規定の仕方からも、控訴審においては書面中心に審理を進めようとしていることが窺われます。
しかしながら、控訴審においては、第一審の判決を覆すことが目的となっており、第一審判決が誤っていることについて、当事者が裁判官に直接アピールできる場は法廷に限られます。私が弁護人に選任されている事件においては、必ず被告人の方には出廷をお願いしております。
2.形式的な裁判
一審の裁判所においては、書面で裁判所に提出するものであっても、その概要を法廷で読み上げるなど、法廷での手続を傍聴するだけで、その内容が分かるように手続は進捗していきます。しかしながら、控訴審においては、裁判の前に書面を提出することが多く、法廷では、その書面の内容を確認するだけの形式的な手続に終始するものが多いです。
そこで、弁護人が十分な弁護活動を行わず、成り行きに身を任していると、控訴審における公判期日はものの5分で終わってしまいます。控訴趣意書の内容を確認するだけの形式的な手続となってしまうのです。
しかしながら、法廷の場で何もできない訳ではありません。新しい証拠を採用させるための活動であったり、短時間でも再度被告人の話を聞いてもらうように請求することで、そのような手続がとられることは珍しくありませんし、法廷の場で何らかの手続が行われた場合には、事前に提出した書面では引用することのできなかった事実が増えているわけですから、法廷の場において、新たにこちらの主張を裁判所に伝えることは可能です。
控訴趣意書を提出した後にも、弁護士の役割は存在するのです。
既に、一度結論が出されている内容について、再考を求めるわけですから、こちらに与えられた機会は、十分に活かす必要があります。
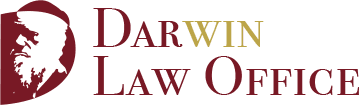
 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー