薬物事件にはどんな法律が適用されるのか。薬物別に適用される法律の違いや量刑を解説(後編)
前編では、覚せい剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法(以下、「麻薬向法」といいます。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「薬機法」といいます。)が、どのような薬物を規制しているのかについて解説させていただきました。 そこで、今回は、各法律に違反してしまった場合に、どのような刑罰が科されることになるのかについて解説させていただきます。 また、よく、日本で規制されている薬物であっても、その薬物を合法に使用できる国で使うことは問題ないのではないかとのご質問もいただきますので、この点についても解説させていただこうと思います。
薬物犯罪における考慮要素

行為態様
前編では、どのような薬物が、どのような法律によって規制されているのかについて解説させていただきましたとおり、まずは問題となっている薬物が、どの法律に違反することになるのかが問題となります。 どの法律が問題となるのかが明らかとなった場合、その次に問題となるのは、その薬物とどのように関わってしまったのかという点です。 薬物事犯の多くは、違法な薬物を「使用」したか、「所持」したことによって、捜査機関によって逮捕されています。 覚せい剤の成分が含まれる水溶液を体内に注射する場合でも、単純に口から飲む場合でも、炙った覚せい剤の蒸気を吸入する場合でも、何らかの形で体内に覚せい剤成分を摂取する場合には、「使用」にあたります。 また、「所持」についても、違法な薬物を複数人が利用する場所で保管していた場合に、誰かが一人で「所持」してのか、複数名で共同して「所持」していたのかについての判断が難しいことはありますが、「所持」という概念が問題となることは少ないように思います。 その他の行為態様としては、輸入、製造(栽培)、譲渡、譲受等があります。譲渡や譲受については、実際に違法な薬物を使用していた訳ではありませんが、違法薬物の害悪を拡散しているという意味で、使用や所持よりも重い刑罰が科されることもあります。
営利性
薬物事犯において、もっとも弁護人が気にするのは、営利性の有無です。使用については、営利の目的で使用するということは考えにくいですが、その他の行為態様については、営利目的があったかどうかによって、科される刑罰の重さが大きく変わってきます。初犯の薬物犯罪については、多くの場合、執行猶予付きの判決が宣告されますが、営利性が認められた場合には、初犯であっても実刑判決が宣告され、直ちに刑務所に服役させられることもあります。 営利性があるかどうかは、実際に薬物を売却している証拠が存在する場合もありますが、多くの場合は量によって判断されます。自分だけで使うにしてはあまりにも多い量を所持していた場合には、営利目的で所持していたものと認められることがありますし、多数の人間に売却し易いように、小分けにして管理していた場合等にも、営利性が認められることがあります。
その他の考慮要素
前科前歴がある場合には、前刑から相当期間が経過していなければ、執行猶予付きの判決を再度宣告してもらえる可能性は低く、執行猶予期間を経過していたとしても、基本的には実刑判決が宣告されることになります。 また、前科前歴以外に重視される考慮要素としては、営利性までは認められない場合であっても、やはり違法薬物の量になります。量が多ければ多いほど、その違法性は高まることになりますので。 前回のコラムでも解説させていただきましたが、同じ「麻薬」として分類される薬物であっても、含まれている成分によって、刑罰の軽重に影響を与える場合があります。
法定刑の一覧表
 以上のように、薬物犯罪における量刑を判断する際には、様々な考慮要素が検討されることになりますから、各法律が定めている法定刑を比較しても、直ちに刑罰の軽重を予想できるわけではありませんが、主要な薬物犯罪についての法定刑を次の表にまとめてみました。
以上のように、薬物犯罪における量刑を判断する際には、様々な考慮要素が検討されることになりますから、各法律が定めている法定刑を比較しても、直ちに刑罰の軽重を予想できるわけではありませんが、主要な薬物犯罪についての法定刑を次の表にまとめてみました。
| 法律名 | 行為態様 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 覚せい剤取締法 | 輸入、輸出、製造 | 1年以上の懲役 |
| 営利目的での輸入、輸出、製造 | 3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金 | |
| 所持、譲り渡し、譲り受け | 10年以下の懲役 | |
| 営利目的での所持、譲り渡し、譲り受け | 1年以上の懲役及び500万円以下の罰金 | |
| 麻向法 | ジアセチルモルヒネ等についての輸入、輸出、製造 | 1年以上の懲役 |
| ジアセチルモルヒネ等についての営利目的での輸入、輸出、製造 | 3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金 | |
| ジアセチルモルヒネ等についての所持、譲り渡し、譲り受け等の行為 | 10年以下の懲役 | |
| ジアセチルモルヒネ等についての営利目的での所持、譲り渡し、譲り受け | 1年以上の懲役及び500万円以下の罰金 | |
| ジアセチルモルヒネ等以外についての輸入、輸出、製造 | 1年以上10年以下の懲役 | |
| ジアセチルモルヒネ等以外についての営利目的での輸入、輸出、製造 | 1年以上の懲役及び500万円以下の罰金 | |
| ジアセチルモルヒネ等以外についての所持、譲り渡し、譲り受け等の行為 | 7年以下の懲役 | |
| ジアセチルモルヒネ等以外についての営利目的での所持、譲り渡し、譲り受け | 1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金 | |
| 大麻取締法 | 輸入、輸出、栽培 | 7年以下の懲役 |
| 営利目的での輸入、輸出、栽培 | 10年以下の懲役及び300万円以下の罰金 | |
| 所持、譲り渡し、譲り受け等の行為 | 5年以下の懲役 | |
| 営利目的での所持、譲り渡し、譲り受け | 7年以下の懲役及び200万円以下の罰金 | |
| 薬機法 | 業として、輸入、販売、所持 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科 |
| 輸入、販売、所持 | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科 |
なお、有期懲役刑の上限は20年とされていますので(刑法第12条1項)、懲役1年以上等と規定されている法定刑における有期懲役の上限は20年になります。また、営利目的で薬物犯罪を犯した場合、その経済的利益をはく奪するために懲役刑と同時に罰金刑についても科されることがあります。懲役刑と罰金刑の双方を科すことを併科といいます。
海外であれば適法に薬物を使用できるか

国外犯の規定
これまで、日本における薬物の規制について解説してきました。しかしながら、大麻については、その使用を合法としている国や地域が存在することは広く知られています。また、コカインを抽出することのできるコカの葉についても、嗜好品として伝統的に嗜んでいる地域も存在します。 これらの地域において、日本では違法とされている薬物を使用・所持することで、日本法によって処罰されることはあるのでしょうか。実際に、捜査機関からの取調べを受けた方からの相談を受けたことはありますが、一般的な質問としてよく耳にする内容です。 まず、確認していただきたいのは、刑法第2条は、「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。」と定めており、殺人罪等の犯罪行為については、日本国外で行われたものについても、日本の刑法を適用する旨を定めています。ですから、刑法第2条が適用される犯罪の場合、日本国外で行った行為であっても、日本の刑法が適用されることになるのです。
薬物犯罪に国外犯規定が適用されるか
では、薬物犯罪に刑法第2条は適用されるのでしょうか。例えば、大麻取締法第24条の8は、「第24条、第24条の2…の罪は、刑法第2条の例に従う。」と定めていますので、大麻の所持、栽培、譲渡等についての行為に対しては、刑法第2条が適用されることになります。 他にも、覚せい剤取締法や麻向法にも、同じような規定が存在します。 そうすると、仮に、大麻等を合法としている地域において大麻を所持した場合、その地域の法律に違反することはなくても、日本の法律に違反したとして、刑罰が科されることになりそうです。実際に、外務省は、カナダにおける大麻の合法化を契機に、上述したような理由で、大麻が合法化されている地域においても大麻に手を出すことのないように注意喚起を行っています。 この点については反論もあります。大麻取締法等の規定をよく見ていただくと、「大麻を、みだりに…輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」等、「みだりに」という文言が付されていることが分かります。 日本国内で違法な薬物を用いる場合、そのことが正当化されることは考えにくいところですが、その薬物が合法とされている地域において用いる場合に、「みだりに」に用いたとは言えないと解釈しているものもあります。
小括
個人的には、上述したとおり、問題となっている薬物を合法なものと扱っている地域において、その地域の法律に違反しない行為なのであれば、日本の法律で違法とされている薬物と接した場合であっても、わざわざ日本の法律を適用して処罰する必要性は薄いように感じています。 しかしながら、外務省の注意喚起を見る限り、日本の捜査機関が、そのような行為を確認した場合に、薬物犯罪として立件する可能性は否定できません。 やはり、日本国外であっても、日本で規制されている薬物を用いるのは避けるべきでしょう。
薬物事件における弁護活動
薬物事件については初犯であれば執行猶予をつけてもらえるとの印象をお持ちの方が多いように思いますし、実際にも執行猶予をつけていただける事案がほとんどです。
しかし、それは単純な所持や使用に関する罪の場合に限られ、前科がない場合であっても、営利目的で大量の薬物を所持していたのではないかという容疑がかけられると、実刑判決が宣告され、長期間に亘り、刑務所で服役することになってしまう可能性は否定できないのです。
また、営利目的によるものとして起訴されない場合であっても、自分自身が使用していただけでなく、周囲に譲渡しているのではないかと疑われる場合には、逮捕され、勾留された後、なかなか保釈が許可されないというケースが極めて多いです。
起訴されてすぐに保釈が許可されない場合、多くの事案においては勾留期間が2か月を超えることになります。2か月もの間、警察署の留置場や拘置所に勾留されてしまえば、日常生活に大きな影響を及ぼします。
そこで、保釈の許可を得るための弁護活動が必要になるのですが、保釈を得るために、捜査機関の取調べに積極的に応じ、必要以上の内容を供述することによって、より営利目的で所持していたのではないかということを疑われる可能性もあり、この点についての弁護方針の策定には細心の注意が必要となります。
ですから、違法な薬物を所持していたという単純な事案であっても、求められる弁護活動まで単純なものとなるという訳ではありません。薬物事件についての経験が豊富な、刑事事件の弁護士によるサポートを受けることが極めて重要になるのです。
まとめ
今回は、薬物犯罪について、その量刑を、薬物や行為態様毎に解説させていただきました。また、日本では違法である薬物を外国で用いた場合に、日本で刑罰を科されることになるかどうかについても解説させていただきました。 薬物犯罪は、被害者のいない犯罪とされています。しかしながら、覚せい剤や麻薬等の薬物は、使用者の心身を蝕むものです。薬物に依存してしまうことで、人生を大きく狂わされてしまった方を多く見てきました。当然、御家族等にも大きな影響を及ぼします。 御家族や自分自身を被害者とする犯罪だといっても過言ではないと思っております。安易に薬物に頼るのは避けるべきですし、一時の安易な判断で過ちを犯してしまった場合には、二度と同じ過ちを犯すことの内容に、薬物犯罪について精通している弁護士に依頼することをお勧めいたします。 弊所では薬物犯罪についても多くの解決実績を有しておりますので御気軽にご相談ください。
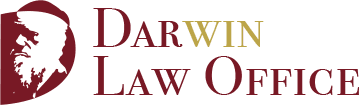




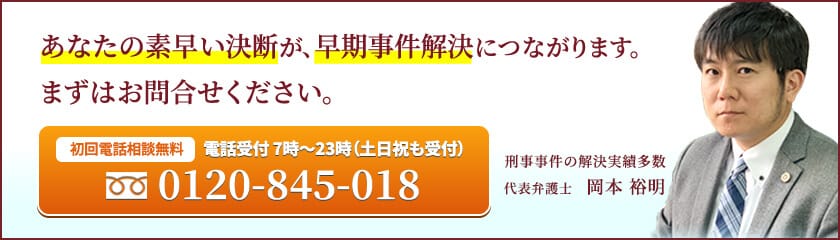

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー