1.少年審判を行うことなく終えられるケースもある
少年事件においては全件送致主義が採用されていますので、原則として検察官の段階で事件が終結することはなく、全ての事件が家庭裁判所に送致されることになります。
しかしながら、検察庁から送致を受けた家庭裁判所が、全ての事件についての審判を行うという訳ではありません。審判を行うかどうかの判断について、少年法は次のように定めています。
少年法
第19条1項 家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。
第21条家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければならない。
このように、「審判に付することができない」場合や、「審判に付するのが相当でないと認めるとき」には、審判を開始しない決定が下され、少年事件はその段階で終了することになるのです。
もっとも、詳しくは少年事件における不起訴処分で解説させていただきましたが(こちら を御確認ください。)、家庭裁判所に送致された段階で、「犯罪の嫌疑がない場合」又は「家庭裁判所の審判に付すべき事由」が認められていることになりますから、「審判に付することができない」といえるケースは稀です。少年事件を数多く担当してきましたが、20歳未満の少年について、「審判に付することができない」ことを理由に、審判不開始決定を得たことはありません。
そこで、審判不開始決定を求めるためには、「審判に付するのが相当でない」ことを付添人から家庭裁判所にしっかり主張する必要があります。
2.審判不開始決定となく終えられるケースもある
では、どのような場合に審判不開始決定を受けることができるのでしょうか。
少年審判は、少年院送致や保護観察等、少年の更生のための処分を決めるために行われる手続です。そこで、改めて審判を行ったり、何らかの処分を下したりしなくても、十分に更生に向けた環境が整備されているとの印象を与えることができれば、審判不開始決定を受けることができます。
そして、審判不開始決定を受ける場合、調査官等による調査を受けた上で、審判不開始決定が下される場合と、調査官からの接触すらないまま、審判不開始決定が決められる場合があります。
少年や少年の両親に、少年の犯罪行為(少年法においては「非行」といいます)を真摯に受け止めてもらうために、家庭裁判所の手続を経験してもらうという考え方もあり得ますが、付添人とすれば、家庭裁判所の力を借りることなく、自身の指導によって、更生環境を整備できるように努めるべきです。
そうだとすれば、付添人等による指導で十分であることを調査官に理解してもらうために、家庭裁判所に送致された後、付添人から詳細な報告書を家庭裁判所に送る必要があります。また、そのような活動を行ったとしても、調査官が少年や少年の保護者との面接を望むことは多くあります。
調査官面接が行われた場合であっても、審判不開始決定を受けることは可能なわけですから、面談の際に、少年の行為がどのような原因に基づくものであるのか、その原因を踏まえたときに、今後の再非行防止策としてどのようなことを考えているのかという点について、しっかりとお話することができるように準備しておく必要があります。
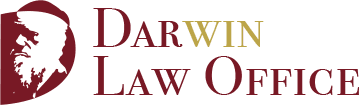
 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー