目次
1 時間が限られているため、直ちに勾留請求を却下するように働きかけなければなりません
検察官が勾留を請求した場合であっても、それだけで被疑者の勾留が決まるわけではありません。被疑者を勾留する権限を有しているのは裁判官になりますので、裁判官が検察官の勾留請求を認容するかどうかが問題となります。ですから、弁護人としては、勾留が請求されてしまった後、直ちに裁判官に対して、勾留請求を却下するように動かなければなりません。
裁判官は、検察官からの勾留請求についての判断を行う前に、被疑者と面談する必要があります。この手続を勾留質問と言います。
刑事訴訟法第61条
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
勾留質問は、東京23区内の警察署が担当している事件の場合には、検察官による勾留請求の翌日に行われることが多く、他の地域では、検察官による勾留請求の後、直ちに行われるケースが多いです。
したがって、検察官の勾留請求の後に弁護人を選任したのでは、弁護人が被疑者に面会する時間的余裕すらない場合があります。
弁護人としては、検察官が勾留を請求した事実を確認した場合には、直ちに、裁判官に対して勾留請求を却下するように働きかけなければなりません。
2 勾留が請求されたからと言って諦める必要はありません
検察官が勾留を請求したということは、検察官は、被疑者による逃亡や罪証隠滅の可能性があると判断したことになります。だからと言って、裁判官が検察官と同様に判断するとは限りません。
2017年度の検察統計調査によると、97357件の勾留請求が認容されたのに対して、勾留請求が却下されたのは3901件に過ぎません。数字だけ見ると4%にも満たない数字ですが、この中には、弁護人の選任が間に合っておらず、何らの弁護活動も行えなかった結果として、勾留が決定されてしまっているものもあります。
弁護人が選任されていない場合、裁判官は、捜査機関から提供された資料のみを前提に、勾留請求についての判断をすることになります。検察官としては、裁判官に勾留を認めて欲しいわけですから、被疑者による逃亡や罪証隠滅を基礎づける資料を裁判官に提出することになりますし、そのような資料のみを前提に判断した場合には、裁判官の判断と検察官の判断が同一のものになってしまっても仕方ありません。
弁護人から、被疑者に有利な資料を提供することによってはじめて、裁判官による適切な判断に期待することができるのです。
3 勾留が認められてしまった場合の準抗告
裁判官が検察官の勾留請求を認めてしまった場合であっても、まだ諦める必要はありません。裁判がの判断に対して不服を申し立てることも可能です。
刑事訴訟法第429条
裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
一 忌避の申立を却下する裁判
二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
三 鑑定のため留置を命ずる裁判
この手続を準抗告といいます。
準抗告については、裁判所の司法統計によると、11166件の申立があった中で認容されたのは2205件となっており、勾留を決定した裁判を覆すことは統計上も非現実的なものとはなっておりません。
一方で、準抗告は、裁判官の判断が間違っていたことを、裁判所に認めさせなければなりませんから、相当に説得的な申立書を作成しなければなりません。具体的には、勾留の理由は必要性を欠くことについて、その裏づけとなる事実を引用し、当該事実についての疎明資料を提出しなければなりません。
私達は、何度も準抗告の認容決定をいただいてきました。勾留が決定されてしまった後でも、早期の釈放を目指すことは可能なのです。




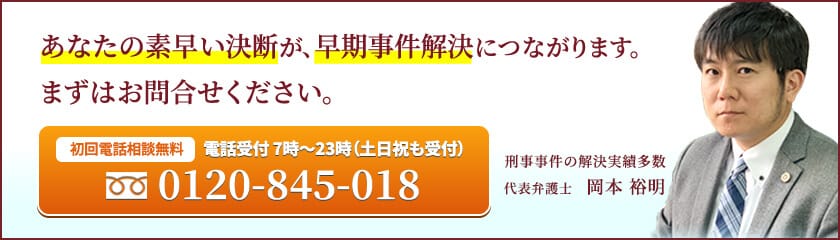

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー