執行猶予が得やすくなる?執行猶予に関する法改正について
- 執行猶予制度についても法改正がなされ、「再度の執行猶予」を付すための要件が緩和された。
- 一方で、執行猶予を取り消すための要件も緩和されており、所謂弁当切りのための弁護活動を行うことができなくなった。
- 社会内での更生可能性がこれまで以上に重視されることとなるため、弁護人、被告人だけでなく、被告人の家族らも諦めることなく、社会内での更生環境を整備する必要がある。
ここ数年は刑事法に関する法改正案が頻繁に議論されています。このコラムでも、侮辱罪についての議論や少年法に関する年齢引き下げの議論などについて解説させていただきました。
他にも懲役刑と禁錮刑を統一化した上で、拘禁刑という新しい刑罰を設けるなど、大きな法改正について議論されてきましたし、そのほとんどについては実際に改正されることが決められています。
内容については、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)と「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年法律第68号)にまとめられており、令和4年6月17日に公布されています。
この法改正の内容については、上述したように様々なものが含まれていますが、その中に執行猶予制度に関係するものも含まれています。
令和3年度の司法統計年報によると、地裁の刑事通常第一審事件の終局区分は、46735人の被告人に対して、27571人に対して全部執行猶予付きの判決が宣告されているようです(なお全部執行猶予付き判決とは別に971人に対して一部執行猶予付きの判決が宣告されているようです)。
この割合は令和2年度においても同様の数値でしたから、半数以上の被告人に対して執行猶予付きの判決が言い渡されていることになります。
また、令和3年度の犯罪白書によると、令和2年における再犯者率は49.1%と半数近くが再犯者であることも報告されており、執行猶予に関する法改正が及ぼす影響は大きいものと予想されます。
今回のコラムでは、法改正によって、執行猶予制度がどのように変わるのかについて解説させていただきます。

目次
1.現行法における執行猶予の在り方
(1)執行猶予を付す要件

まずは、現行法がどのような場合に執行猶予を付すことができる旨を定めているのか確認しましょう。
刑法
(刑の全部の執行猶予)
第25条
1項 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わっ た日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
まずは、原則として3年以下の懲役刑等の言い渡しを受けた被告人が対象となるので、3年以上の懲役刑を言い渡された場合には、執行猶予を付すことはできません。
また、5年以内に禁錮刑以上の刑の言い渡しを受けた方も、原則としては執行猶予を付すことができません。ただし、前刑に執行猶予が付されている場合、当該執行猶予期間の経過によって、刑法第27条が「刑の言渡しは、効力を失う」と定めていますので、基本的には出所してから5年以内に刑の言渡しを受けた場合に、執行猶予を付けることができないという意味になります。
一方で、例外的に、情状に特に酌量すべきものがある場合には、執行猶予を本来であれば付すことができない状況下であっても、1年以下の懲役刑が新たに言い渡された場合に限り、執行猶予を付すことができます。このことを「再度の執行猶予」と言います。
なお、前に言い渡された執行猶予付きの判決について、保護観察にも付されている場合には、情状に特に酌量すべきものが認められたとしても、「再度の執行猶予」を付すことはできません。
(2)執行猶予を取り消す要件

次に、現行法がどのような場合に執行猶予を取り消すことができる旨を定めているのか確認してみましょう。
刑法
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第26条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
1号 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の 全部について執行猶予の言渡しがないとき。
2号 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、 その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
3号 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1号 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2号 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
3号 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑 の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
基本的には、執行猶予期間中に再度刑事裁判を受けることとなり、その新たな裁判において執行猶予がつかない判決(実刑判決)を言い渡された場合に、刑の執行猶予が取り消される旨が定められていると理解できます。
ここで注意すべきなのは、新しい裁判によって実刑判決が宣告されたことが必要である旨が定められており、執行猶予期間中に何らかの犯罪行為に及んだとしても、それだけでは執行猶予が必要的に取り消される訳ではないということです。
執行猶予期間中に新たな判決が言い渡されなければ取り消されないことになるからこそ、執行猶予の取消を避けるために、新たな裁判に関する判決が確定するのを避ける弁護活動が求められるのです。そのためだけに、特に事実に争いがない場合であっても裁判を引き延ばすことを、所謂弁当切りと言います。
2.法改正後の執行猶予を付す条件

では、上述した内容がどのように変わるのでしょうか。改正案を確認したところ、執行猶予を付す条件としてこれまで理解されていた基本的な部分については、大幅な変更点はないように思います。
法改正によって変更があったのは、「再度の執行猶予」についてです。
これまでは、1年以下の懲役刑を言い渡された場合にしか「再度の執行猶予」が付されることはありませんでしたから、執行猶予期間中に一定程度の更生が認められる場合であっても、新たに犯した罪について、1年以下という極めて短期の刑が妥当するような罪でなければ「再度の執行猶予」の対象にはなりませんでした。しかし、今回の改正によって、1年以下という部分が2年以下に引き上げられました。例えば、薬物事犯については、2度目の犯罪であっても、1年以下の刑罰は不適当であっても2年以下の懲役刑を言い渡されることは珍しくないため、「再度の執行猶予」が言い渡される余地が広がったと考えることはできそうです。もっとも、薬物事犯の場合、再犯までに一定の期間が認められなければ、執行猶予期間が経過した後でも実刑判決が言い渡されることが多いので、この法改正によって二度目までは執行猶予が付されるということにはならないであろう点にも注意が必要です。
もう1点は、保護観察中の再犯についてです。従前は、保護観察中の再犯については執行猶予を付す余地がありませんでした。しかし、法改正によって、保護観察中の再犯についても「再度の執行猶予」を付すことができるようになりました。もっとも、「再度の執行猶予」期間について保護観察が付された場合で、その保護観察中に更に犯罪に及んだ場合には、執行猶予を付すことはできない旨が定められています。
3.法改正後の執行猶予が取り消される条件

以上のように、執行猶予を付す要件については、法改正によって緩和されているものということができ、「再度の執行猶予」を得やすくする法改正だということができます。
では、執行猶予を取り消す条件についてはどうでしょうか。刑法第26条や第26条の2については、特に大きな修正はなされていません。しかし、次の刑法第27条2項が新設されることによって、執行猶予が取り消され得る状況は、大幅に増えることが予想されます。
改正刑法
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第27条
2項 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から…刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間、引き続きその効力を有するものとする。
刑法第27条1項は執行猶予期間の経過により、当該執行猶予付きの判決の言渡しの効力が消滅する旨を定めているのですが、この2項によって、新たに犯した罪についての判決が言い渡されるまでは、前刑の効力が消失しないこととなったのです。
その結果、執行猶予期間中に新たな罪を犯した場合、その新たな罪についての判決を遅らせたとしても、その判決に執行猶予が付されていない限りは、前刑の執行猶予が取り消されることになります。つまり、所謂弁当切りのための弁護活動は無意味となるのです。
4.執行猶予期間中の再犯に関する弁護活動について

以上のとおり、執行猶予制度に関する法改正は、執行猶予を付する要件を緩和して、「再度の執行猶予」を得やすくする側面がある一方で、執行猶予が取り消される可能性を増加させる側面もあるものと整理できます。
確かに、被告人の執行猶予を取り消すべきかどうかを考えるにあたっては、執行猶予期間中に再度犯罪に及んでしまったことが重要なのであって、執行猶予期間中に新たに犯した罪についての判決が言い渡されるかどうかは重要ではありませんし、弁当切りを目的とする弁護活動に正当性があるようには思えませんでした。
したがって、執行猶予が取り消され易くなった点については、弁護人目線としても大きな違和感はありません。
むしろ、「再度の執行猶予」を得るための条件が緩和されている訳ですから、これまで以上に「再度の執行猶予」を得られるような弁護に努める必要があるはずです。そして、その際には、前回執行猶予付きの判決を言い渡されており、再度罪を犯してしまったにもかかわらず、社会内での更生が妥当であることを裁判官に理解させる必要があります。
そのためには、再度罪に及んでしまった背景や原因などを踏まえた上で、当該背景や原因を解消するために、前刑の言渡し後から取り組んできていることを正確に主張する必要があるのです。
5.まとめ

今回は、執行猶予制度の法改正の内容について解説させていただきました。原則として、執行猶予期間中に再度罪を犯してしまった場合には、社会内での更生の機会を活かせなかったわけですから、実刑判決が相当であると考えられてしまっても仕方ありません。
それでも、刑務所に服役させるよりも、引続き社会内で更生に努めさせた方が、本人のためになるケースが一定程度認められるからこそ、今回のような法改正に繋がっている訳ですし、弁護人としても被告人の家族としても安易に「再度の執行猶予」を諦めるべきではありません。
実刑判決を受け入れてしまう前に、一度弁護士に御相談いただければと思います。





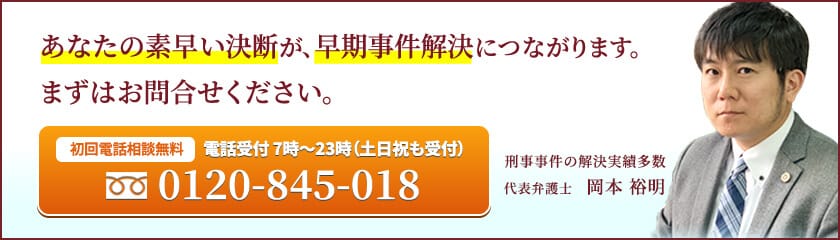

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー