再保釈は原則として許すべきではないのか(法制審部会の要綱案をみて)
- 法制審議会刑事法(逃亡防止関係)部会において、被告人の公判期日への出頭及び刑の執行の確保を目的とする刑事法の整備案が昨年末にとりまとめられた。
- 要綱案の中には、再保釈を判断する基準についての明文の定めも提案されているが、その内容は再保釈の判断を厳格化するものである。
- 再保釈の判断を適切に行うにあたって、要綱案に沿った改正は反対であり、今後も継続的な議論が望まれる。
法務省の法制審議会刑事法(逃亡防止関係)部会において、被告人の公判期日への出頭及び刑の執行の確保を目的とする刑事法の整備案が昨年末にとりまとめられています。
このコラムでも、法務省内に設置された検討会のとりまとめ案等について、性犯罪についての改正や侮辱罪の法定刑引上げについて解説させていただきましたとおり、刑事法分野の法改正に向けた動きは活発に行われております。
その中でも、逃亡防止関係の議論の内容は、多くの争点を含むものであり、実際に法改正がなされた場合には、多くの刑事事件において大きな影響を及ぼす可能性があります。
外国籍の被告人に対するGPSの装着や、保釈請求にあたっての監督者の選任等、刑事事件を扱う弁護士として目を引くトピックが多いのですが、私は過去に再保釈に関する論文を寄稿したこともあり、再保釈に関する改正について興味を抱いております。
そこで、今回は、再保釈について解説させていただきたいと思います。

再保釈について
第一審判決宣告後に請求する保釈をいう
刑事訴訟法上には保釈について定めた規定は存在しますが、「再保釈」という単語は用いられておりません。
実務上、「再保釈」とは、第一審の段階で保釈を許可された被告人に対して、第一審判決が実刑(執行猶予が付されない懲役刑のことを言います。なお、一部執行猶予が付された懲役刑が宣告された場合、被告人は刑務所に服役することになりますから、一部執行猶予付きの判決も実刑判決の一つと理解されています。)判決を宣告したことで、保釈の効力が消滅した後、控訴審における審理中の身体拘束を防ぐために、改めて請求する保釈のことを言います。
なお、第一審判決後に行う保釈請求は、第一審判決前に保釈が許可されていたかどうかによって、手続や要件が変わることはありませんから、第一審判決前に保釈が許可されていない被告人が、第一審判決後に初めて保釈を請求する場合においても、「再保釈」と同様の問題が生じますが、今回のコラムでは第一審判決前に一度保釈が許可されている被告人の保釈に絞って解説したいと思います。
法律上の定め
上述したように、「再保釈」という単語は刑事訴訟法において定められておりませんが、「再保釈」と第一審判決宣告前に請求する保釈は、刑事訴訟法上その扱いが区別されています。
まずは条文を確認してみましょう。
刑事訴訟法
第89条
1項 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯
したものであるとき。
2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる
罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3号 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものである
とき。
4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められ る者若し
くはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖怖させる行為
をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。第343条
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。第344条
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第60第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。
保釈については、第89条と第90条が定められています。第89条は、いくつかの事項に該当しない限りは保釈を認めなければいけないという権利保釈について定めており、第90条は裁判官の裁量によって保釈を認める裁量保釈について定めた規定です。
いずれの形で認められた保釈であっても、第343条によって、実刑判決が宣告された場合には失効するため、刑が確定して収監されるまでの間は、留置施設に勾留されることになります。
そこで、留置施設から釈放させるためには、再び保釈を請求する必要があるのですが、第344条によって、実刑判決が宣告された後は、法89条の権利保釈を請求することは認められず、法第90条の裁量保釈しか請求することが認められないという規定になっています。
再保釈についての許可基準
以上のとおり、再保釈においては、第89条が適用されないという以外に特別な規定は定められておりません。
そこで、再保釈を認めるかどうかを判断するにあたっては、第一審判決宣告前における第90条に基づく保釈の判断と同じ基準を用いて判断することを刑事訴訟法は前提にしているように思います。
しかしながら、既に第一審判決において実刑判決が宣告されている以上、同じ基準で保釈を許可することで、不必要な控訴の数や逃亡者の数が増加する可能性があることを理由に、再保釈についてはより制限的に理解すべきであるとの見解も根強く存在します。
このような見解についての争いは、制限説と非制限説の対立として、学説上も争われているところではありますが、このコラムでは学術的な対立には入り込まないようにしたいと思いますので、興味のある方は、「再保釈請求の許可基準に関する理論と実務」に私の考えをまとめてありますので、御参考にしていただければと思います。
法制審部会の要綱案
条文案
今回の法制審部会がとりまとめた要綱案では、禁錮以上の実刑判決宣告後における裁量保釈の要件を明確化すべきだとされており、次のような条文案が提案されています。
確認してみましょう。
要綱案
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、刑事訴訟法第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならないものとし、ただし、当該判決の宣告にかかわらず、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでないものとすること。
つまり、「逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由」が認められない限りは、「保釈が許可されないことについての不利益の程度が著しく高い場合」でなければ、再保釈は許可されないこととされているのです。
再保釈の判断を厳格化する内容となっている
法制審部会の要綱案は、「保釈を許すには…不利益の程度が著しく高い場合でなければならない」と定めていますから、基本的には再保釈を現状よりも厳しく判断することを前提としているものと理解せざるを得ません。
現時点において上述した制限説を前提に再保釈に関する判断がなされているのであれば、上記要綱案は、現状の実務の運用を明文化しただけだと理解することもできそうですが、法制審部会の中では、現在の実務が制限説に沿って運用されている訳ではなく、明文を定めることによって再保釈の判断が厳しくなることに懸念を示す委員もいらっしゃいました。
今回の法制審部会は逃亡防止を図るための整備を主眼としているはずですから、保釈が許可されている被告人の扱いなどについて議論がなされるべきで、保釈の許可基準自体の厳格化・緩和等についての議論ではなかったはずです。
このような要綱案が示されたことを非常に残念に感じております。
要綱案の問題点
今回の要綱は「逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由」が認められなければ、基本的には再保釈を否定することを相当とするような内容となっています。
勾留や保釈の判断に際して重視される「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」ではなく、逃亡のおそれを問題視しているのは、既に問題となる事実についての審理が行われており、罪証隠滅工作が現実的に不可能となっていることがほとんどであることに加え、被告人を引続き勾留する主眼が、刑の執行を確保する点にあるからと考えられています。
しかし、罪証隠滅を疑う理由があることで勾留されていた以上、裁判所に多数の証拠が提出され、罪証隠滅の可能性が低下したのであれば、被告人の身体拘束を正当化する事情は消失しているように思います。
この点について、一審判決が有罪判決を宣告している以上、無罪推定の原則は一歩後退せざるを得ないということを言われることがあります。
確かに、一度は有罪判決を宣告されている訳ですが、我が国では三審制がとられており、一審で宣告された判決が確定している訳ではありませんから、無罪推定の原則が後退しているとは考えられません。
実刑が宣告されたことによって、その刑の執行から免れたいという動機が、判決の宣告前よりも現実化する側面はあるかもしれませんが、その点を一つの考慮要素として、改めて保釈の可否を判断すれば足りるはずです。
特に、再保釈の場合には、実際の裁判を担当した裁判官が保釈の可否を判断することになる訳ですから(控訴審係属部に書類が送致された場合には、控訴審の裁判官が担当することになりますが)、実際の裁判を行う前になされた保釈請求と比較して、様々な事情を踏まえた判断が可能となるはずです。
にもかかわらず、「逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由」という点を過度に重視することになる、要綱案について私は反対です。
再保釈を目指す弁護活動
以上のように、再保釈に関する法改正が見込まれており、その方向性としては再保釈を厳格化するものが予想されます。そのような中で再保釈の許可を得るためには、改正経緯について十分に理解している刑事事件の弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。
また、法改正がなされる前の段階であっても、再保釈の許可を得ることは困難なものとなっています。多くの被告人が第一審判決において実刑判決を宣告される前までは、保釈が許可されていたにもかかわらず、実刑判決を宣告された後、控訴審については身体を拘束されたままで裁判の準備を行わざるを得ない状況に陥っているのです。
本来的には、通常の保釈請求よりも再保釈の方が認められ易くあるべきだと思います。それは、既に第一審の判決が宣告されている以上、有罪判決を証明するための証拠は全て裁判所において取調べ済みで、証拠隠滅が不可能な状態にあることと、第一審の裁判の際に保釈が許可されており、逃亡を図ることなく判決期日に出廷している以上、逃亡を疑う相当な理由も解消されているといえるはずだからです。
にもかかわらず、再保釈が許可されない場合、証拠隠滅や逃亡を疑う相当な理由が認められないことだけでなく、再保釈を許可すべき何らかの事情を準備する必要があります。例えば、依存症を理由に犯罪行為に及んでしまった場合においては、通院や入院の必要性を強く主張することも考えられます。しかし、それまで一切通院や入院の実績がなければ、その必要性を主張することは困難になります。
したがって、再保釈の許可を受けるためには、実刑判決が宣告された場合に備えて、第一審の段階から準備を進めておく必要があります。どのような理由であれば再保釈を認めてもらえるかについては、ケースバイケースとしか言えませんから、保釈についての経験が豊富な刑事事件の弁護士のサポートが非常に重要となるのです。
まとめ
今回のとりまとめ案が直ちに改正法の内容となる訳ではありませんから、今回のコラムで解説させていただいた「再保釈」に関する論点以外にも、継続的に議論を続けていく必要があります。
被告人等の逃亡を防止する方法として、保釈の判断を厳格化するという結論が安易に取られることがないように、私達も今後の議論を注視していきたいと思いますし、積極的に意見を発信していきたいと思います。











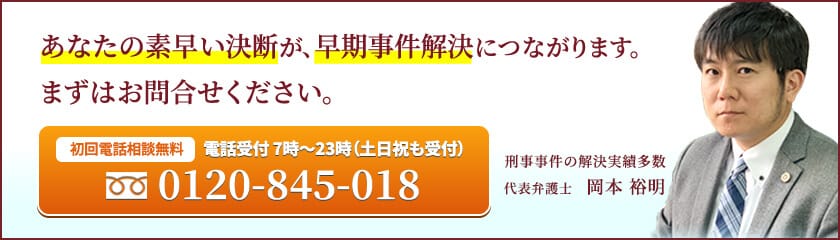

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー