目次
1 終局処分に向けて、目的を明確化する必要があります
逮捕・勾留がなされている場合、検察官は、勾留満期日までに、被疑者に対する処分を決めなくてはなりません。検察官による処分は、大きく分けて、不起訴処分、略式起訴、正式起訴の3種類になります。これらの検察官の処分を終局処分といいます。
また、不起訴処分には様々な理由が存在します。
法務省 事件事務規定第75条2項
不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(1) 被疑者死亡
被疑者が死亡したとき。
(2) 法人等消滅
被疑者である法人又は処罰の対象となるべき団体等が消滅したとき。
(5) 親告罪の告訴・告発・請求の欠如・無効・取消し
親告罪又は告発若しくは請求をまって論ずべき罪につき、告訴、告発若しくは請求がなかったとき、無効であったとき又は取り消されたとき。
(8) 確定判決あり
同一事実につき既に既判力のある判決があるとき。
(9) 保護処分済み
同一事実につき既に少年法第24条第1項の保護処分がなされているとき。
(10) 起訴済み
同一事実につき既に公訴が提起されているとき(公訴の取消しがなされている場合を含む。)。ただし、第8号に該当する場合を除く。
(11) 刑の廃止
犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
(13) 時効完成
公訴の時効が完成したとき。
(14) 刑事未成年
被疑者が犯罪時14歳に満たないとき。
(15) 心神喪失
被疑者が犯罪時心神喪失であったとき。
(16) 罪とならず
被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、又は犯罪の成立_を阻却する事由のあることが証拠上明確なとき。ただし、前2号に該当する場合を除く。
(17) 嫌疑なし
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(19) 刑の免除
被疑事実が明白な場合において、法律上刑が免除されるべきとき。
(20) 起訴猶予
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
分かり易いもののみを取り上げても、不起訴となる理由には様々なものがあります。どの理由による場合であっても、不起訴処分であることに変わりはないのですが、どの理由に基づいた不起訴処分を目的とするのかによって、弁護士のとる弁護活動は大きく変わってきます。ですから、終局処分に向けた弁護活動を行うに当たっては、どのような処分によって事件を終わらせることを目的とするのかについて、明確にしておかなければなりません。
2 無罪主張を前提とする弁護活動
上述したように、不起訴処分には様々な理由があります。ですから、どの理由に基づく不起訴処分を目的とするのかによって、弁護活動は大きく変わってきます。無罪を主張する場合であっても、どの理由に基づく不起訴処分を目的とするのかによって、とるべき弁護方針は異なり得るのです。
例えば、嫌疑不十分を理由とする不起訴処分を目的とする場合、多くの事案においては、捜査機関に対して不必要な情報を提供することがないように、取調べに対しては黙秘権を行使することになると思います。逆に、罪とならないことを理由とする不起訴処分を目的とする場合、被疑者の行為を正当化する事情については、被疑者が捜査機関に対して伝えなければ、捜査機関が当該事情を看過する可能性もありますから、捜査機関に対して積極的に被疑者の言い分を伝えていくことになるかもしれません。例えば、正当防衛が成立することを理由とした不起訴処分を目的とする場合、相手方による暴行の存在については、相手方が正直に捜査機関に伝えていない可能性も高く、被疑者側から捜査機関に伝える必要があるかもしれません。
一方で、捜査機関に何らかの供述をした場合には、被疑者の不利となる情報も提供される可能性がありますから、事件の現場が明確に記録されている防犯カメラの映像等がある場合等、罪とならないことを理由とする不起訴処分を目的とする場合であっても、黙秘すべき事案も十分考えられるのです。
以上のように、無罪を主張するような事案においても、その内容如何によって、弁護方針が変わることは大いにあり得るのです。
3 罪を認めている場合の弁護活動
罪を認めている場合であっても、不起訴処分によって事件を終結させることはあり得ます。親告罪において被害者との示談がまとまれば、告訴が取り消されたことを理由とする不起訴処分を得ることができますし、その他の犯罪類型であっても、前科をつけるほどの犯行ではないと判断された場合には、起訴猶予処分を得ることができます。
このような場合、犯罪自体の悪質性が軽微であることを主張することはもちろんですが、被疑者が反省していることを示して、再犯可能性が低いことを主張する必要もあります。このことは、事件事務規定第75条2号(20)が、「被疑者の性格」を考慮要素として挙げていることからも明白です。
捜査機関に対して黙秘権を行使したのでは、反省の情は伝わりませんが、不必要な情報を提供することで、犯罪行為が悪質であると判断されたり、常習性を疑われてしまっては逆効果となってしまいます。
また、罪を認める場合、前科が存在したり、罪が重い場合等、起訴猶予処分を見込めない事案も存在します。そのような場合でも、罪を認めつ弁護方針を定めた場合には、まず正式な裁判を回避して、略式起訴による手続で、事件を終結する可能性を探ることになると思います。
略式であっても起訴手続ですから、裁判所が関与することになりますが。略式起訴の場合、裁判所に送られるのは事件の記録のみで、被疑者の方が裁判所に行く必要はなくなります。略式起訴の後、裁判所が、適切な罰金額を定めて、その結果が後日郵送されることになるのです。
略式罰金であっても前科がついてしまうことに変わりありませんし、罪を認めることと、全てを捜査機関に打ち明けることは同じではありません。弁護方針に沿った活動を行うにあたって、捜査機関に提供すべきでない情報も存在します。
4 正式起訴に備えた弁護活動
捜査段階における終局処分の中で、正式起訴は被疑者にとってもっとも重い処分になりますから、正式起訴を目的とする弁護活動はあり得ません。しかしながら、正式起訴になった場合に備えた弁護活動は必要になります。
例えば、正式起訴された後、まず考えるべきは保釈の請求になります。保釈請求書の起案や、保釈請求書に添付する資料については、捜査段階で一定程度収集しておく必要があるでしょう。また、捜査段階で正式起訴がやむを得ない事案だと判断される場合には、保釈の請求に対して、検察官が強い反対意見を述べることがないように、一定程度、捜査機関に対して情報を提供する(取調べに応じる)といった手段も考えられます。
逆に、正式起訴の場合には、裁判の手続が行われるわけですから、裁判の場で足を引っ張るような供述調書を作成させたくありません。
以上のとおり、どのような処分を目的とするのかによって弁護方針は変わりますし、同じ処分を目的にする場合であっても、弁護方針が一律に決まるわけではなく、個別具体的な事案に即して、最適な弁護方針を定める必要があります。








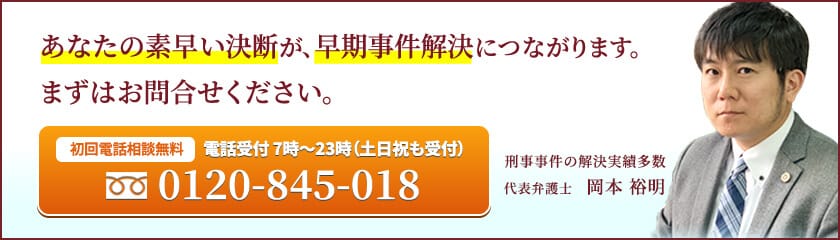

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー