起訴・不起訴を決める検察官って何者?-検察官の役割・捜査編
- 検察官の主たる職務は、刑事事件の公訴を提起して、裁判所に対して法令に基づいた判断を求めることであり、その前提として捜査活動がある
- 検察官は、様々な事情を考慮して、被疑者の起訴、不起訴を決めている
- 弁護士は、捜査の期間において、検察官が不起訴を決めることに繋がる事情を提供したり、不起訴が相当である旨の意見を申し入れたりしている
今回のコラムの題材を探していた頃、某国民的アイドルグループのメンバーであった方が主演していた刑事ドラマが地上波で再放送されていました。このドラマが放送されていた当時は、刑事ドラマでは警察官にスポットライトが当たることがほとんどだったのですが、この刑事ドラマでは検察官にスポットライトが当たっており、ドラマの出演者も相俟って視聴率を席巻していた記憶があります。ドラマの各話には、起訴、不起訴という言葉が出てきていましたが、そもそも検察官が何をしているのかを知らない方は多くいらっしゃるのかなと思います。検察官の役割を知ることで、弁護士の活動が捜査に大きな影響を与えていることが分かります。今回は、検察官の役割・捜査編と題して、解説していきます。

検察官とは
検察庁法
第3条
検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
第4条
検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。 第6条
1項 検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。 2項 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、刑事訴訟法の定めるところによる。
刑事訴訟法
第191条
1項 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 2項 検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
第193条3項
検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
検察官の職務の概要
検察官の職務については、検察庁法に規定があります。同法4条は、「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。」と規定しています。この中でも代表的な職務は、「刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求」すること、つまり、刑事事件の公訴を提起して、裁判所に対して法令に基づいた判断を求めることと言い換えることができるでしょう。そして、公訴を提起するか否かを判断するために、検察官は、犯罪について捜査をし(検察庁法6条1項)、検察事務官も検察官の指揮の下、捜査を行っています(同条2項)。また、検察官は、犯罪の捜査に当たり、警察官と互いに協力して職務に当たっています(刑事訴訟法192条)。
そもそも、公訴が何なのかについては、後述致します。
検察官になるには
検察官は、原則として、司法試験に合格し、司法修習という研修を修めなければなることのできない職業です(検察庁法18条1項1号)。これは、裁判官であっても、弁護士であっても同様です(裁判所法43条、弁護士法4条)。裁判官も検察官も弁護士も、それぞれの職務がどのような内容であるのかについて実習した上で、任命され又は登録されます。そのため、裁判官も弁護士も、検察官がどのような職務に当たっているのかを学んだ上で各自の職務に当たっているのです。
因みに、検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事に振り分けられています(検察庁法3条)。もっとも、刑事事件の捜査や裁判の中で接することがあるのは検事又は副検事がほとんどです。
起訴・不起訴とは
刑事訴訟法
第247条
公訴は、検察官がこれを行う。
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
起訴とは公訴を提起することで、不起訴とは公訴を提起しないことです。公「訴」を提「起」する、公「訴」を提「起」しない(不)と、言葉通りなのですが、そもそも公訴って何なのかというのが大きな疑問になるでしょう。
公訴とは、国家刑罰権の発動のため、被疑者の犯人性、犯罪の有無について審理を求めることをいうとされています。簡単に言えば、犯罪の疑いをかけられている者(被疑者)を裁判にかけて、犯人であるかどうか、犯罪が成立するかどうかを裁判官に判断してもらうことを指します。
日本では、原則として、検察官が被疑者を起訴する権限を持っています(起訴独占主義)。例外として、検察審査会による起訴相当の議決に基づいて公訴を提起するパターン(検察審査会法41条の9以下)や特定の犯罪について告訴又は告発がなされたが検察官がこれを起訴しなかった場合にその不起訴処分に不服があるとして起訴を求めていく手続である準起訴手続(刑事訴訟法262条以下)などがあります。もっとも、例外のルートで刑事事件が起訴されることは非常に稀です。そのため、日本においては、検察官のみが起訴をする権限を持っているという理解で差し支えないといえます。
検察審査会につきましては、弊所の過去のコラム「検察審査会とは何か」で解説していますので、興味のある方はぜひ参照ください。
日本では、検察官は、刑事事件を必ず裁判にかけなければならないという制度にはなっていません。犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができます(刑事訴訟法248条)。この考え方を、起訴便宜主義といいます。
令和3年7月1日時点において、日本の検察官の人数は、2739人です。これに対し、令和元年の検察庁新規受理人員は90万0752人です。日本全国の全ての犯罪を起訴するとなると、人員も時間も何もかも足りません。また、犯罪の内容も万引きから殺人まで様々であり、犯行に及んだ経緯や犯人の境遇からすれば、裁判にかける必要のない者もいます。そのため、検察官は、捜査によって客観的な証拠を収集し、関係者の話を聞き、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を総合的に判断して、犯人を起訴するか不起訴とするかを決める裁量を与えられているのです。
日本の刑事裁判における有罪率は、約99%と言われています。有罪率が極めて高い理由は、検察官が、被疑者が犯人であることと犯罪が成立することについて、証拠をもって立証することができるという確証を持った上で起訴していることによります。被疑者が犯人であることや被疑者の犯罪の成否について立証するには不十分な証拠しかない場合には、検察官が被疑者を起訴することは考えにくいです。
被疑者が犯人であること及び犯罪が成立することは証拠をもって十分に証明することができるが、被疑者の事情を総合的に判断して、起訴をしないことを起訴猶予ということがあります。起訴猶予も不起訴処分の1つです。
被害者が全く処罰を望んでいない場合には、検察官は、起訴しないことがあります。この場合、検察官が起訴をしない理由は、被害者の処罰意思が犯罪の要件になっているパターンと犯罪の要件は満たしているが起訴を猶予しているパターンがあります。
弁護士の役割
それでは、弁護士は、検察官が捜査をする中でどのような活動をしているのでしょうか。
検察官が犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況等を考慮して、起訴するか不起訴とするかを判断していることは先ほど申し上げたとおりです。そのため、弁護士は、この考慮要素を前提にした上で、検察官に汲むべき事情と汲むべきでない事情を理解してもらうような意見を申し入れ、犯人を起訴すべきではないと訴えかけているのです。例えば、弁護士は、捜査担当の検察官に対し、捜査担当の検察官が入手することのできない被疑者の誓約書や被疑者家族の嘆願書等の資料を提出したり、被害者との示談の状況を報告し、あるいは、示談書を送付したりして、捜査期間中に生じた被疑者の新事情を伝えることが挙げられます。
刑事訴訟法
第197条
1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 2項 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。 3項 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。 4項 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。 5項 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
また、弁護士は、被疑者に対し、黙秘権(刑事訴訟法198条2項)、供述録取書の増減変更権(同条4項)、供述録取書への署名押印拒絶権(同条5項ただし書)等の権利があることを説明し、捜査機関という公権力に対抗し得る権利を用いて、力の差を埋めるように促しています。
不起訴を目指す弁護活動
以上のとおり、検察官に起訴され裁判を受けることとなった場合、被告人の被る不利益は極めて大きなものとなりますから、起訴される前の捜査段階における刑事事件の弁護士の役割は、不起訴を目指すことになります。このことは、罪を認めている場合であっても、罪を否認している場合であっても変わりませんし、罪の大小によっても変わりません。
また、不起訴には様々な理由があり、被疑者が亡くなってしまった場合であっても不起訴処分はなされますし、嫌疑不十分を理由とする不起訴処分もあります。一方で、犯罪を証明するための証拠が十分にあった場合であっても、犯情が軽微で十分に反省していると認められる場合には、起訴猶予という理由で不起訴処分となることもあります。
そこで、刑事事件の弁護士としては、どのような理由に基づく不起訴処分を目的とするのか、ハッキリと定めた上で弁護方針を固める必要があります。嫌疑不十分を目指す場合には、取調べに対して黙秘することがほとんどだと思いますし、起訴猶予処分を目指す場合には、示談交渉や更生環境の整備等を行う必要があります。
逆に、嫌疑不十分を目指す場合であっても、不起訴処分の可能性を高めるために、示談交渉を行う事もあり得ますし、刑事事件の弁護士が、目的を達成するために、具体的なアドバイスを行うことが求められるのです。
さらに、どのような弁護方針でどのような理由による不起訴処分を目指す場合であっても、被疑者が逮捕、勾留されている場合よりも、身体拘束されていない方が、弁護活動の幅は広がります。したがって、不起訴処分を得るためにも、逮捕、勾留を回避するための弁護活動は重要になるのです。
まとめ
検察官は、被疑者を裁判にかけるか否かを決める権限を独占している官庁です。検察官が被疑者を裁判にかけるか否かを判断するには、捜査中における弁護士による弁護活動が大きな影響を与えています。











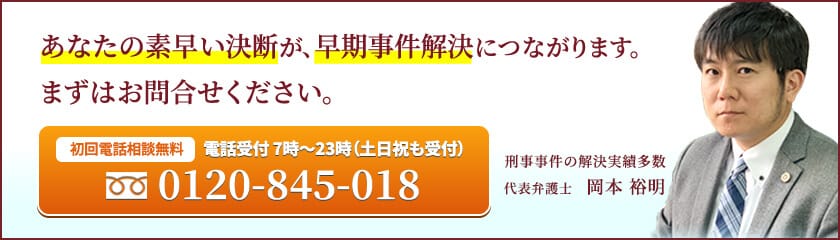

 電話をかける
電話をかける メニュー
メニュー